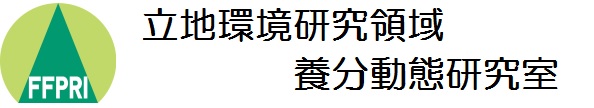 |
 |
|
|
| ニホンジカが森林の窒素循環に及ぼす影響 |
1.主な研究内容-ニホンジカが森林の窒素循環に及ぼす影響- 森林と土壌に様々な影響をあたえるニホンジカ 近年、日本各地でニホンジカ(以下,シカという)が増加し、造林木が食害されて大きな問題となっています。さらに、シカは林床の植物を食べることで低木層の消失、林床植生の種組成の変化や現存量の減少などを引き起こします。シカが森林の植物の状態を変えると、植物−土壌間の養分循環が変化して森林が保持している養分量にも影響する可能性があります。そこで、奈良県大台ヶ原、栃木県の日光地域などの天然林で、シカ排除柵の内外で林床植物—土壌間の窒素養分循環量を調査してきました。 大台ケ原では、シカがいる状態では林床植生であるミヤコザサの地上部現存量はシカを排除した場合の5分の1以下と少なく、ミヤコザサ-土壌間の窒素循環量が小さいこと、土壌移動の増加が引き起こされることなどが明らかになりました。一方、奥日光地域ではシカ排除により低木層が繁茂した場合に、植物にとって利用しやすい窒素養分量が土壌中に増えることが明らかになりました。今後もシカと林床植生と土壌養分の関係を解明し、それらの関係に基づいてシカの管理法を考える必要があります。  大台ケ原の写真:(左)大台ケ原では、シカが林床に優占するミヤコザサを食べていて、まるで芝刈り機で刈ったようにミヤコザサの高さが低くそろっています(1997年〜2006年ごろの状況)。(右)シカを排除する囲いの内側では、シカを排除して4年ほどでミヤコザサの高さと量が回復しています。  日光の写真:(左)日光では林床にシカの不嗜好性の植物が優占しています。(中)日光における不嗜好性植物の1つ、シロヨメナ。 (右)日光ではシカを排除して10年ほどで低木層が回復しています(写真の右上の部分)。 関連する読み物 1)大台ケ原 <シリーズ>森めぐり(7)(森林科学62:26-27, 2011-06-01) 2)ニホンジカによるササの採食が森林の窒素循環に及ぼす影響 : 大台ヶ原の事例を中心に <特集>ササのユニークな生態とその管理・利用(森林科学69:18-21, 2013-10-01) ページトップへ戻る |
| 森林総合研究所ホームページへ戻る 養分動態研ホームページへ戻る |
|
|