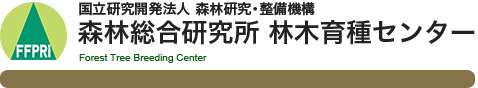ここから本文です。
カラマツ種子の確保に向けた取組(続編)
令和4年1月26日
吾妻森林管理署管内にカラマツ精英樹採種園の「田代第1採種園」(群馬県吾妻郡嬬恋村)があり、カラマツ種子の安定的な生産体制を確立することを目的に吾妻署、群馬県林業試験場、森林総合研究所林木育種センターの3機関により協定を締結し取り組んでいます。昨年8月にも着花促進処理と着果調査をご紹介しましたが、本稿ではその後の状況を報告します。
着花促進処理は、昨年度から採種園内を数区画に分け、区画内から数本の剥皮処理木を選び、区画順に行っています。これは、その年の気候によって豊凶が左右されるため、毎年処理をしつつ豊作年を逃さないようにする必要がある一方で、剥皮は採種木の樹体に負担をかけるため、同一個体に複数回処理する場合は前回の剥皮処理部位の回復状況を見て判断する必要があるためです。処理は、一本の幹に対して樹皮の剥皮を2ヶ所行います。まず、2cm程度の幅で樹皮を半周程度剥皮し、次に幹の直径の約1/2程度上下どちらかにずらして、反対側を同様に剥皮します。この時、剥皮した部分の上下の重なりが幹周囲長の10%程度となるようにします。
5月12日、22本の採種木について、木材チョークで剥皮部分に印をつけ、ノコギリで切り込みを入れ、大工ノミで剥皮する作業を行いました。これらの剥皮木については、来年春に着果が期待されます。また、昨年剥皮処理した区画について、剥皮木と過去の調査で着果が見られなかった採種木を中心に樹勢回復および着花枝の充実を図るために採種木の周囲2mの位置に深さ30cm程度の穴を8箇所掘り、有機質が配合されたペレット型の肥料と化成肥料の埋め込みを行いました(2ヶ月後、有機質肥料の穴はすっかり掘り返され、荒らされていました。野生動物によるものと思われます。一方、化成肥料のみを埋め込んだ穴では掘り返しは見られませんでした)。
6月3日、採種園全域から標本木(剥皮木含む)を選んで着果調査を行ったところ数本に着果が見られました。昨年剥皮処理した個体の中には樹冠全体に着生しているものがあり、剥皮木以外では全体に着生する個体はありませんでしたが、まばらに着生しているものはみられました。また、昨年剥皮処理した中には枯損した採種木もありました。これは剥皮幅が少し広かったためと思われました。
8月上旬に種子の充実を調査しました。採種木から採取する方向を変えて数個採取し、球果の巾1/3の位置で切断したところ、5~8の白い胚乳が確認されました。その後の吾妻署による採種作業では全体(2.29ha)で球果15kg弱(種子約700gに相当)が採取されました。
来年度以降も継続して処理を行い、3機関が連携してカラマツ種子の安定的な生産体制の確立を目指した取組を進めていきたいと思います。
 |
 |
 |
| 環状剥皮 | 施肥 | 球果切断による種子の充実状況 |
(指導普及・海外協力部 指導課)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.