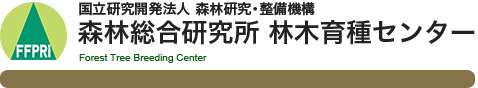ここから本文です。
カミキリホイホイによるスギカミキリの捕獲調査を行いました(R元~3年度)
令和4年8月24日
近年、府県等から少花粉品種等の種苗配布要望が増加しており、限られた採穂母樹の維持管理が重要となっています。関西育種場及び四国増殖保存園では、スギカミキリやヒメスギカミキリ(以下、スギカミキリ類とする)によると思われる母樹の被害が以前と比べ頻繁に見られるようになってきました。母樹がスギカミキリ類に加害されると枯損するリスクがあるため、そのリスクを最小限に抑えるために令和元年度よりカミキリホイホイを用いた捕殺調査を実施しています。今回はこれまで3年間の取組について紹介します。
使用したカミキリホイホイはアースバイオケミカル株式会社製で、特殊粘着剤を使用しており殺虫成分はなく、環境への負荷が少ないものとなっています。設置場所は関西育種場及び四国増殖保存園のスギ原種園等で、一部枝枯れし衰弱した母樹やヤニが漏出した母樹に設置しました(写真)。カミキリホイホイは帯状の紙製で片面が粘着シートになっており、設置木の樹幹下部に粘着面を内側にして帯状に巻き付けました。スギカミキリ類の成虫は樹体内で越冬し、4月頃に成虫となって脱出するため、成虫の脱出時期を見計らい活動を開始する前の2~3月に設置しました。カミキリホイホイは、スギカミキリ類を捕獲することができ、これらによる被害の蔓延防止が期待できます。そこで今回の取組では、スギカミキリ類の捕獲頭数を調査しました。
令和3年度は、関西育種場のスギ・ヒノキ原種園に460枚(1本当たり1枚)、四国増殖保存園のスギ原種園に282枚(1本当たり1枚)をそれぞれ設置しました。その結果、関西育種場と四国増殖保存園をあわせて、スギカミキリ類514頭が捕獲されました(写真)。令和元年度から令和3年度までの3カ年の取組状況は、下表のとおりとなります。関西育種場では、捕獲頭数は、ほぼ横這いで推移していますが、3年間継続したことにより、1,000頭以上捕獲することが出来ました。今後も設置を続けることで、スギカミキリ類の増加を抑えることが出来るものと思われます。一方、四国増殖保存園では大幅に捕獲頭数が減り、取組の成果と捉え、今後も設置を継続することで、採穂母樹の生育状況等の経過を観察したいと考えております。
(関西育種場)
 |
 |
 |
| 設置した対象木(部分枯れ(写真左)及びヤニ漏出木(写真右)) | 捕獲したスギカミキリ類 | |

カミキリホイホイによるスギカミキリの捕獲調査を行いました(R元~3年度)(PDF:598KB)