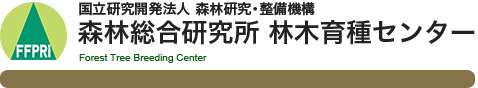ここから本文です。
九州森林管理局の若手職員を対象に業務研修を実施しました
令和4年9月21日
九州森林管理局から依頼を受け、8月30日に九州森林管理局の若手職員(採用後2年目)18名を対象に業務研修を実施しました。
室内講義では、まず、日本の人工造林面積や山行き苗木生産量等の推移について説明を行ったうえで、他の地域と異なり九州育種基本区ではさし木によるスギ山行き苗木の生産が圧倒的に多い現状であることや背景について説明を行いました。
今回の研修生は若手職員で通常業務の中で育種・育苗に携わっていないことから、第一世代精英樹・エリートツリー(現時点では第二世代精英樹)・特定母樹について、選抜方法や指定基準など詳細な説明を行いました。その中で、研修生からは「第三世代、第四世代へと交雑育種が進むといずれ成長の改良効果に限界があるのでは?」、「樹高成長が良く、形状比が高い傾向があると根張りはどうなのか?」、「エリートツリーが第一世代と比べて肥大成長より樹高成長の方が良いと風倒被害の心配は?」等々質問があり、「限られた母集団を用いた場合、将来的には一世代あたりの改良効果は徐々に小さくなることが考えられる」、「根張りについては調査事例がなく不明であるが、試験地や採穂園などでこれまで風倒の事例は生じていない」、等と説明・回答しました。
次に、森林の適正な整備の推進のため、優良種苗の安定生産・適正な流通の確保が重要であること、このために林業種苗法において、系統が明らかな優良種苗を造林者に確実に届ける措置等が定められていることを説明しました。
続いて採穂台木の意義、穂木の生産について、樹木の繁殖(増殖)の方法について紹介し、同じ個体、系統でも採穂部位や樹齢による発根性が異なること、普通枝と萌芽枝とでは発根率に大きな差が生じること等の理由から採穂台木が利用されていることを説明した後、場内圃場にて、原種園の採穂台木を見学していただきました。その後、特定母樹に指定されているスギ九育2-203(植栽9年次)を見学し、風倒被害等を受けずに優れた初期成長の特性を示している様子を実感していただきました。
今回の研修は2時間程度の短い時間でしたが、九州育種基本区の苗木生産の現状、エリートツリーや特定母樹などの選抜・指定までの流れ、優良種苗の普及の重要性などの理解を深めていただけたかと思います。
 |
 |
| 室内での講義の様子 | 特定母樹(スギ九育2-203)の見学 |
九州森林管理局の若手職員を対象に業務研修を実施しました(PDF:364KB)