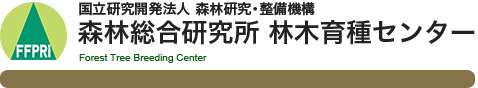ここから本文です。
技術指導のご紹介
令和4年12月14日
林木育種センターでは、都道府県等からの要望に応じて種苗の増殖や採種園等の造成管理に関する技術指導を行っています。今年度実施した技術指導のうち、岐阜県の例をご紹介します。
岐阜県郡上市の白鳥林木育種事業地において、岐阜県担当者及び東濃桧採種園・白鳥林木育種事業地の各管理職員を対象に、ヒノキのつぎ木増殖とスギミニチュア採種園の樹形誘導について、実技を交えながら技術指導を行いました。
ヒノキのつぎ木増殖について、室内でつぎ木の方法と管理について座学を行った後、場所を移してつぎ木増殖の実技を行いました。つぎ木作業については、採種木の補植用などで管理職員がこれまでも実施しているため、高い技術が維持されていました。一方、つぎ木作業後の管理面について、「つぎ木の活着は良いが、その後の養苗過程で枯死が多くみられる。養苗中の生存率を高く維持するために気をつけた方がよい点にはどういったことがあるか」との質問があり、これに対し、つぎ穂を保湿するために取り付けた袋を外す場合は晴天を避ける、横風による穂木の乾燥を避けるように袋の上部を開放した後に少し様子をみてから取り外すなど、急激な湿度変化が生じないように配慮することが肝要との説明をしたところ、「これまでの取り外し作業では湿度変化の重要性について認識していなかったので、今後は湿度管理にも注意しながら作業を行いたい」とのことでした。
スギミニチュア採種園の樹形誘導では、1回目の剪定は採種作業がしやすくなるよう採穂木の高さ調整、2回目は枝の間引きと長さの調整などによる採種木の骨格決め、3回目以降は樹形の維持と採種量を確保するための萌芽枝育成を目的に行うことを説明しながら、実技を行いました。
今回伺った白鳥林木育種事業地には、昭和39年に造成したスギ採穂園がありました。造成後58年経過していますが、採穂木としての樹形が維持され、さし穂用の萌芽枝も多数発生しており、丁寧に管理することで長く利用できることを改めて感じました。
今後も都道府県等の要望に応じた林木育種事業に関する技術指導を、わかりやすく効果的に実施できるよう努めていきたいと考えています。
(指導課)
 |
 |
 |
| ヒノキのつぎ木 | ミニチュア採種園樹形誘導 | 昭和39年造成 スギ採穂園 |