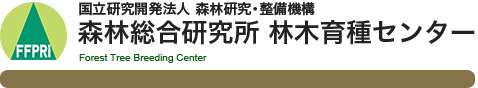ここから本文です。
「いぶき山イブキ樹叢」へ里帰りした後継樹の現状
令和5年1月25日
林木育種センターの所在地・茨城県日立市十王町にある「いぶき山イブキ樹叢」は、樹形が竜や虎など様々な形に見える自然の妙がすばらしいと江戸時代の文献にも紹介されている国指定天然記念物です。天然分布するイブキが少ない福島県~茨城県~千葉県の太平洋岸地域において、大正時代に出版された「常陸多賀郡史」によると明治末期頃まではその名の通り鬱蒼とした林が形成されていたようですが、次第に樹勢が衰えるにつれてこの貴重なイブキには滅失のおそれも出てきました。
そこで、林木育種センターでは平成8年度に「いぶき山イブキ樹叢」から採取した穂木を用いてイブキの苗木をさし木で増殖してきました。また、この天然記念物を管理してきた旧十王町は、平成13年度から「いぶき山イブキ樹叢」の樹勢を回復するための取り組みとして、現地においてイブキの生育を妨げる木々の除去や土壌の改良、後継樹の補植等を行うこととなり、林木育種センターに協力を要請しました。この取り組みによって、3本のイブキからさし木によって増殖していた4本の苗木が、後継樹として引き渡され、平成14年3月に現地に植栽されました。
それから20年が経ち、令和5年1月に日立市郷土博物館の協力で、「いぶき山イブキ樹叢」に植栽された後継樹の現状を確認する機会が得られました。現地を調査した結果、生存している後継樹が1本確認され、植栽時には70cm程度であった樹高は4.2mに、幹の直径は胸の高さで6.6cmにまで成長していました。
「いぶき山イブキ樹叢」のように、高齢や被害が原因で衰弱した天然記念物などの中で特に保存する価値と緊急性が高い樹木の後継樹を増殖して現地に里帰りさせる取り組みは、平成15年度に開始した「林木遺伝子銀行110番」として引き継がれています。
(探索収集課)
 |
 |
| 左:「いぶき山イブキ樹叢」 右:生存が確認された後継樹(点線は幹の位置) | |
「いぶき山イブキ樹叢」へ里帰りした後継樹の現状(PDF:814KB)