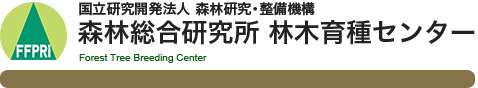ここから本文です。
「種子・胞子・組織培養を使った保全フォーラム:小笠原の絶滅危惧種に注目して」を開催しました
令和5年1月31日
令和4年12月19日(月曜日)に公益社団法人日本植物園協会と森林総合研究所林木育種センターが共催でオンラインフォーラム「種子・胞子・組織培養を使った保全フォーラム:小笠原の絶滅危惧種に注目して」を開催しました(http://www.syokubutsuen-kyokai.jp/introduction/uploaded/officeinfo/00131_01.pdf(外部サイトへリンク))。
植物の生息域外保全の中でも、種子や胞子を冷凍庫などの低温環境で保存する方法は限られたスペースで多様な種、個体の保存を可能にする費用対効果の高い方法です。これまで保存されてきた種子や胞子を用いて将来それら種の野生復帰に利用することが期待されていますが、まだ知見が不足しており、未だ復帰技術が確立しているとは言えない状況です。
日本国内でも小笠原諸島は絶滅危惧植物種がもっとも集中する地域のひとつで、12種が環境省の保護増殖事業の対象となっていますが、種子・胞子の保存と、これらを使った野生復帰は十分に実施されていません。今回のフォーラムは種子・胞子ならびに組織培養苗を使って小笠原の絶滅危惧種の保全を推進することをめざし、生息域外での保存を促進するとともに現地で保全に関わる方々が交流できる機会として開催されました。
イベントでは、まず日本植物園協会の遊川氏による主催者挨拶と英国キュー王立植物園ミレニアム・シードバンクのHardwick博士によるメッセージから始まり、生物多様性保全において種子などによる生息域外保存の重要性が紹介されました。続いて種子保存課題と発芽に関する知見の重要さを紹介する以下の5題の講演が行われました。
- 「種子保存の概論」森林研究・整備機構 森林総合研究所 林木育種センター 木村 恵
- 「種子を使った野生復帰」国立環境研究所 西廣 淳
- 「種子発芽特性の検証」沖縄県北谷町教育委員会 藤 彰矩
- 「シードパケットを使った野外播種試験」福島大学共生システム理工学類 山下 由美
- 「小笠原での種子・胞子を使った保全の取り組み」東京大学大学院理学系研究科附属植物園 出野 貴仁
次に小笠原での保全事例報告として現地での希少植物の保全について以下の4つの活動が紹介されました。
- 「組織培養技術を用いたオガサワラグワの生息域外保全」森林研究・整備機構 森林総合研究所 林木育種センター 玉城 聡
- 「オガサワラグワをシンボルとした村民参加の森づくり」小笠原村環境課 井上 直美
- 「ホシツルランの種子を使った保全」Islands care 向 哲嗣
- 「遺伝的多様性と地域との連携を考慮したタイヨウフウトウカズラの生息域内・域外保全」京都大学大学院地球環境学堂/大学院人間・環境学研究科 瀬戸口 浩彰
当センター職員の講演者である木村からは、国内外の種子保存に関する研究事例を紹介するとともに、林木育種センターの林木ジーンバンク事業や小笠原で採取された種子の乾燥耐性についての研究成果を紹介しました(写真1)。また、保全事例報告の発表者である玉城からは、日本植物園協会、小笠原村および林木育種センターが共同で実施している「オガサワラグワの里親計画」の進捗状況を紹介するとともに、組織培養技術を用いたオガサワラグワの生息域外保全の取り組みについて紹介しました(写真2)。
フォーラムの最後には9名の講演者が一堂に介し、小笠原の希少種保全に向けた意見交換が行われました。フォーラムには植物園をはじめ、林野庁や環境省、東京都、小笠原村の職員、研究者、NPOスタッフなど様々なバッググラウンドの参加者が参加しました。定員の100人を超える参加登録があり、種子・胞子・組織培養を使った保全への関心の高さがうかがえました。
 |
 |
| 写真1 テトラゾリウム溶液の染色による種子の活性調査。 生存している種子は赤く染まる。 |
写真2 組織培養により増殖し、クローン保存している オガサワラグワの鉢植え苗 |
(育種部育種第二課 遺伝資源部保存評価課)
「種子・胞子・組織培養を使った保全フォーラム:小笠原の絶滅危惧種に注目して」を開催しました(PDF:411KB)