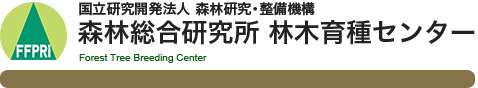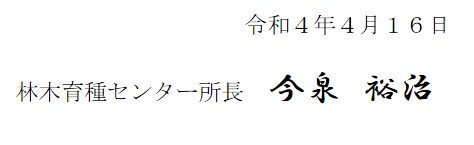ホーム > 業務紹介 > 沿革 > 林木育種センターの歴史 > 所長挨拶
更新日:2022年5月18日
ここから本文です。
所長挨拶
林木育種のさらなる発展を目指して
おかげさまをもちまして、森林総合研究所林木育種センターは、本日、設立65周年を迎えました。
昭和32年に前身の国立中央林木育種場と北海道、九州の各国立林木育種場が国有林野事業の組織として設立されたのを皮切りに、翌33年から35年にかけて東北、関西の各国立林木育種場と長野、奥羽、山陰、四国の各支場が設立されて以降、平成3年に林木育種センター本所・4育種場・4事業場体制に再編され、平成13年に独立行政法人となり、平成19年に旧森林総合研究所と統合するとともに、先端技術を用いた育種技術を開発するため森林バイオ研究センターを新設、その後、平成27年に国立研究開発法人となり、さらに平成29年には国立研究開発法人森林研究・整備機構と名称を変更するなど、変遷を繰り返しましたが、一貫して、国内最大の林木育種機関として、その役割を果たしてきました。
この間、林木育種センターでは全国に配置された育種場とともに、森林管理局(国有林)や都道府県等との連携のもと、成長・形質の優れた品種や病虫害・気象害に強い品種、花粉症対策品種等の開発を進めるとともに、これら品種開発の素材や希少な種等の遺伝資源の収集・保存、林木育種の海外協力などに取り組んで参りました。
これまで全国から選ばれた、およそ九千個体の精英樹について、検定・交配を進め、1,100系統(令和4年3月末)の第二世代精英樹(エリートツリー)を選抜するとともに、間伐等特措法に基づき農林水産大臣から特定母樹382系統(令和4年3月末)の指定を受け、都道府県等の採種園・採穂園への供給を通じて、その普及を図るとともに、さらなる改良効果の発揮を目指して、第三世代への世代交代に向けて取り組んでいるところです。
また、地球温暖化による気候変動への対応、花粉を出さず成長の優れたスギ品種の開発、あるいは新たな需要が期待される早生樹の開発など、高度化・多様化する社会的要請に応えるべく、近年、進歩の著しいゲノム解析技術等を活用した高速育種技術の開発や、コウヨウザン等新たな育種素材の選抜・評価等にも積極的に取り組んでいます。
さらに、再造林の現場へ円滑にすぐれた苗木を供給していくためには、その適切な系統管理を含め、都道府県や間伐等特措法に基づく認定特定増殖事業者等の皆様による採種園等の適切な整備・管理が重要となっています。このため、特定母樹等普及促進会議や林木育種連携ネットワーク等を通じた技術情報の提供や「講習会」又は「技術講習会」の開催等により、これら関係者と一体となった取組を進めています。
森林資源の充実に伴い主伐が増加する中、持続的な林業経営を確立するためには、優良な品種の開発及びその早期普及に取組、森林管理局や都道府県、大学等研究機関、その他関係者各位のご理解とご協力のもと、林木育種のさらなる発展に努めて参ります。
|
|
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.