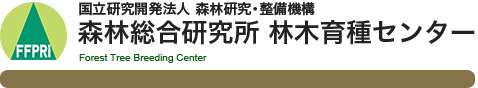ホーム > 業務紹介 > 遺伝資源の収集・保存・配布 > 林木遺伝資源連絡会 > 林木遺伝資源連絡会誌 > 林木遺伝資源連絡会誌【2012 No.2】
更新日:2017年8月29日
ここから本文です。
シコクシラベのつぎ木増殖
| 笹島芳信1)・橋本光司2)・尾坂尚紀3) | ||
| 1)森林総合研究所林木育種センター関西育種場 | ||
| 2)森林総合研究所 総務部 | ||
| 3)森林総合研究所林木育種センター西表熱帯林育種技術園 |
1.はじめに
森林総合研究所林木育種センターでは、貴重な林木遺伝資源を後世へ継承するとともに、試験・研究材料として利用しやすくするために林木遺伝資源の収集・保存に取り組んでいます。
今回、近畿以西の西日本および四国第二の高峰「剣山(標高1,955m)」から「一の森(標高1,879m)」方面に向かう登山道途中に設定されている徳島森林管理署管内の鎗戸林木遺伝資源保存林内(標高約1,850m)から平成19・21・22年度に収集したシコクシラベのつぎ木増殖及び結果について報告します。
2.採穂及び貯蔵方法
通常、つぎ木増殖用穂木の採穂は樹木の休眠期の12~3月に行いますが、剣山は冬期の12~4月上旬頃まで積雪のため入山が出来ず採穂ができないことから、1回目は平成19年11月13日に剣山1~5の5個体、2回目は平成21年4月14日に剣山6~10の5個体、3回目は平成22年4月20日に剣山11~20の10個体の合計20個体から採穂し、1個体から約20本の荒穂を採取しました(写真1,2)。
採穂した穂木は、つぎ木実施時期の4月中旬頃までCTM貯蔵箱に入れ0℃の冷蔵庫で貯蔵しました。なお、1回目に採穂した穂木の貯蔵期間が長かったため、開封後、葉が落ち多少のカビが発生するなど穂木が傷んだことから、2回目からは採穂後すぐにつぎ木ができるように4月に採穂することとしました。
 |
 |
| 写真1 採穂の様子 | 写真2 荒穂 |
3.台木
台木は、1回目はシラベのポット苗、2回目はトドマツのポット苗をガラス温室で、3回目はトドマツを苗畑で、それぞれ購入した苗木を養苗し使用しました。
4.つぎ木方法
つぎ木は、台木が根から十分に水分を吸収し、冬芽が開葉し始めた頃に「割りつぎ法」で行いました。
1)穂づくり
貯蔵しておいた枝の先端部分をつぎ穂とし、芽が3つ以上付いていること、病虫害などで痛んでいないことに注意し、7cm程度の長さに切り取りつぎ穂(写真3)とします。つぎ穂の長さは5cm程度、削り面は2cm程度(写真5)として、くさび形にします。また、ナイフで切る時に邪魔になる葉を丁寧に取り除きます(写真4)。
 |
 |
 |
| 写真3 切り取ったつぎ穂 | 写真4 葉を取り除いたつぎ穂 | 写真5 つぎ穂 |
2)つぎ木部位と台木切り
つぎ木部位は、前年伸びた芯で側枝が輪生している上部5cm程度で切り落としたところに行い、台木はつぎ穂の削り面より少し短い長さで幹の真ん中に切り込みを入れます(写真7)。
 |
 |
| 写真6 台木 | 写真7 台木の切り方 |
3)つぎ穂の挿入
つぎ穂と台木の形成層の位置を確認し、台木の切り下げた部分まできちんと入れ、両方の形成層がぴったりと合うように挿入しますが、台木とつぎ穂の太さが必ずしも同じでないため、片方の形成層同士が合うように挿入します(写真8)。
 |
| 写真8 つぎ穂の挿入 |
4)つぎ穂の巻き締めと癒合剤の塗布及び袋かけ
挿入したつぎ穂と台木をつぎ木テープで巻き締めますが、合わせた形成層がずれないように下方から慎重かつ丁寧に巻き締めていきます(写真9)。
巻き締め後、切り口等の乾燥防止と雑菌の侵入防止のため癒合剤を塗布し(写真10)、また、つぎ穂の乾燥を防ぐため、台木の残りの枝を巻き上げるか、切り落とした枝等を使いつぎ木部位を包み麻ひもで軽く結びます(写真11)。最後に、つぎ木部位の乾燥防止とつぎ穂の葉からの蒸散作用を抑制するため空気穴を空けた厚手のポリエチレン袋を被せビニ帯で止めます(写真12)。
 |
 |
 |
 |
| 写真9 締め付け | 写真10 癒合剤塗布 | 写真11 麻ひもで結束 | 写真12 袋かけ |
5.管理
つぎ木後の管理として、ガラス温室では、寒冷紗等の日覆いは行わず多少日陰に置き自動潅水により管理します(写真13)。
苗畑では、つぎ木床の乾燥と直射日光による急激な気温上昇を防ぐため黒色寒冷紗で覆い管理します(写真14)。
ポリエチレン袋は、ガラス温室と苗畑ともに、つぎ穂の新葉が完全に展開し袋にぶつかる前に袋の上部を切り、数日後に完全に袋を取り外し、さらに数日後に麻ひもを外し段階的に順化します。また、苗畑の黒色寒冷紗は8月下旬頃まで覆い、徐々に寒冷紗の裾を上げ数日かけて順化し撤去します。
 |
 |
| 写真13 ガラス温室 | 写真14 苗畑 |
6.結果
各年度の活着率は表1のとおりです。
平成19年度は29~60%(平均42%)、平成21年度は42~69%(平均57%)、平成22年度は40~90%(平均58%)と個体により活着率に差はありますが、この3年間で剣山のシコクシラベ後継苗木増殖の目的は十分に達成することができました。なお、ガラス温室で増殖した分については、つぎ木を行った次年度春期に苗畑に床替えを行いました。
| 品種名 | 収集年月日 | 増殖年月日 | 増殖場所 | 台木の樹種 | 実行本数 | 活着本数 | 活着率(%) |
| 剣山1~5 | H19.11.13 | H20.4.10 | ガラス温室 | シラベ | 52 | 22 | 42 |
| 剣山6~10 | H21.4.14 | H21.4.16 | ガラス温室 | トドマツ | 136 | 77 | 57 |
| 剣山11~20 | H22.4.20 | H22.4.26 | 苗畑 | トドマツ | 199 | 116 | 58 |
7.おわりに
今回の穂木採取について、四国森林管理局、徳島森林管理署及び徳島県の各担当者の方には、生育場所等のアドバイスや採取等に係る各種手続きにご指導・ご協力をいただきこの場を借りてお礼申し上げます。
今後は、養苗中の苗木を健全に成長させ当育種場内に保存し試験研究用等に活用して参ります。
 |
 |
| 写真15 つぎ穂開葉 | 写真16 現在の様子(苗畑) |
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.