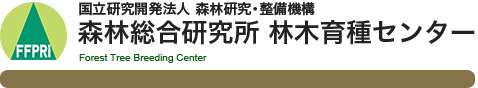ホーム > 業務紹介 > 遺伝資源の収集・保存・配布 > 林木遺伝資源連絡会 > 林木遺伝資源連絡会誌 > 林木遺伝資源連絡会誌【2012 No.4】
更新日:2017年8月29日
ここから本文です。
奄美群島の固有種およびリュウキュウマツ(Pinus luchuensis)等の収集・増殖・保存
| 濱本光 | ||
| 森林総合研究所林木育種センター九州育種場 |
1.はじめに
林木遺伝資源は、木材、果実あるいは医薬品等の形で古くから人類に大きな恵みを与えてきました。また、科学の発展につれて将来も様々な形で人々に大きな恵みを与えてくれると見込まれています。しかし、これらの資源は地球規模の環境の変化等が原因で世界的に減少・絶滅することが危惧されています。このような状況から、地球上に現存するこれらの林木遺伝資源を保全し子孫に伝達するとともに、必要なときに必要な林木遺伝資源を利用できる体制が必要となっています。
そのため、(独)森林総合研究所林木育種センターでは、林木ジーンバンク事業の一環として天然記念物および巨樹・名木等の林木遺伝資源の収集・増殖・保存を行っており奄美群島においては固有種であるワダツミノキ(海神の木、Nothapodytes amamianus)や、マツクイムシ被害が深刻となっているリュウキュウマツ(琉球松、Pinus luchuensis)の球果採取・増殖・保存を行っており、その取り組みを紹介します。
2.奄美群島の概要
奄美群島は、鹿児島市より南西に約400km、沖縄本島より北東に約350km離れた鹿児島県の奄美大島を中心に、徳之島、沖永良部島などの島々で構成されています。その中でも奄美大島は鹿児島市と沖縄本島の中間地点にあり古くから栄えてきました。
奄美大島の植生は、北部の奄美市笠利町にある笠利崎灯台のアダン(阿壇、Pandanus odoratissimus)群落や、中部の奄美市住用町にある「道の駅住用」にマングローブの群生地といった熱帯樹種があるほか、オキナワウラジロガシ(沖縄裏白樫、Quercus miyagii)やスダジイ(須田椎、Castanopsis sieboldii)などの照葉樹も混成しており、多種多様な植生を要しています。
奄美群島においては、マツノザイセンチュウによるリュウキュウマツ(琉球松、Pinus luchuensis)の枯損被害が1990年代から奄美大島の南に位置する加計呂麻(かけろま)島(大島郡瀬戸内町)で発生したのを皮切りに、対岸の奄美大島や南西に位置する徳之島でも続々と被害が発生して深刻な問題となっています。
3.固有種等
奄美群島のアマミカジカエデ(奄美梶楓、Acer amamiense)、ワダツミノキ(海神の木、Nothapodytes amamianus)といった固有種の種子・穂木を平成20年度から関係各位の御協力を頂き収集・増殖・保存を行っており、これまでに採取した固有種等は表-1、表-2のとおりです。
| 年 度 | 採取個体数 | 内 訳 |
| H20 | 40 | アマミカジカエデ:13(2)、ヒロハタマミズキ:2(1)、ワダツミノキ:3、タイワンツクバネウツギ:3、ヒメサザンカ:3(12)、アマミヒイラギモチ:2(2)、リュウキュウアセビ:1、リュウキュウツルマサキ:1、オオシマムラサキ:5、ヒサカキサザンカ:5、リュウキュウベンケイ:1(3)、リュウキュウスズカケ:1 |
| H21 | 35 | アマミカジカエデ:8(47)、シロバナサクラツツジ:1(4)、フトモモ:1(1)、オキナワキョウチクトウ:1(6)、サガリバナ:1、オオシマムラサキ:1、ツゲモドキ:1(4)、ワダツミノキ:5(8)、ヒロハタマミズキ:2(1)、ケラマツツジ:5(8)、ハマジンチョウ:1、タイワンツクバネウツギ:3、リュウキュウミヤマシキミ:1、リュウキュウマユミ:1(4)、ギーマ:1(2)、オキナワウラジロガシ:1、オオバイヌビワ:1、アマミセイシカ:1(73) |
| 計 | 75 |
※()書きは増殖に成功している本数
| 年 度 | 採取個体数 | 内 訳 |
| H20 | 3 | アマミカジカエデ:1、ワダツミノキ:1、アマミヒイラギモチ:1(1) |
| H21 | 6 | アマミカジカエデ:1(8)、ハスノハギリ:1、タイワンウオクサギ:1、リュウキュウモクセイ:1(3)、オキナワツゲ:2 |
| H24 | 9 | シシアクチ:1、イイギリ:1、ハマセンダン:1、ヒイラギズイナ:1、シャリンバイ:1、シマウリカエデ:1、タイミンタチバナ:1、ウラジロカンコノキ:1、ホルトノキ:1 |
| 計 | 18 |
※()書きは増殖に成功している本数
1)ワダツミノキ(海神の木、Nothapodytes amamianus)
|
奄美大島に自生する常緑高木で、石垣島と西表島に植生するクロタキカズラ科クサミズキ(臭水木、Nothapodytes foetida)の変種であることが、京都大学の研究チームによって明らかになりました。抗癌薬イリノテカンの原料となるカンプトテシンという成分が含まれていることが研究結果で明らかになっています。 |
 |
| 固有種「ワダツミノキ(海神の木)」の播種による増殖状況 |
2)アマミカジカエデ(奄美梶楓、Acer amamiense Yamazaki)
|
奄美大島に自生する雌雄異株の落葉高木で、カエデ科カエデ属に属し谷沿いの湿潤な場所を好み樹高は10m程度まで成長します。カジカエデの特徴は葉柄や葉の裏に多数の毛が生えていますが、奄美のものは殆ど無毛です。また、カジカエデの果実には短い軟毛がある他に長い剛毛が生えているのがカジカエデの大きな特徴ですが、奄美のものは短い軟毛だけで剛毛は無く、ル-ペで見なければ無毛のように見え、カジカエデに良く似ています。 |
 |
| 固有種「アマミカジカエデ(奄美梶楓)」のさし木による増殖状況 |
3) リュウキュウモクセイ(琉球木犀、Osmanthus marginatus)
|
奄美大島、徳之島、沖永良部島、沖縄県、台湾、中国華南に自生する常緑小高木で、モクセイ科モクセイ属に属し、岩がちの林縁などに多く自生しています。葉は対生し楕円形で長さ6~15cm、幅2~6cm、葉先は小さく尖ります。果実は黒色で長さ約1cmになります。 |
 |
| リュウキュウモクセイのさし木による繁殖状況 |
4)アマミセイシカ(奄美聖紫花、Rhododendron latoucheae var. amamianum)
|
奄美大島の限られた地域に少数個体が自生する常緑小高木で、ツツジ科ツツジ属に属し林縁や林内に生息しています。旧大島郡住用村(現奄美市住用町)の村木に指定されていました。西表島や石垣島に分布するセイシカ(聖紫花、Rhododendron latoucheae)の変種とされております。
|
 |
| アマミセイシカのさし木による繁殖状況 |
4.リュウキュウマツ(Pinus luchuensis)
リュウキュウマツ(琉球松、Pinus luchuensis)はマツ科マツ属に属し、北は鹿児島県トカラ列島の悪石島から南は沖縄県の波照間島まで分布しており、主に海岸線沿いに自生しています。リュウキュウアカマツ(琉球赤松)とも言われています。
リュウキュウマツは、耐風・耐潮・耐乾燥性に優れ沖縄の気候に適していることから、古来より建築材や薪炭材、サバニ(沖縄古来の漁船)の材料として用いられてきましたが、近年は樹形の美しさから緑化樹種としての需要も増えてきています。反面、シロアリの被害に弱いという欠点があります。
美しい樹形から、奄美市の市木、龍郷町の町木、沖縄県の県木に指定されており、久米島(島尻郡久米島町)にある国指定天然記念物「五枝の松」と伊平屋島(島尻郡伊平屋村)の「念頭平松」は、リュウキュウマツの銘木として知られています。
当場では、リュウキュウマツの遺伝子を後世に残そうと平成20~24年度にかけ、鹿児島県森林技術総合センター(鹿児島県姶良市)と鹿児島森林管理署(鹿児島市)のご協力をいただき、鹿児島県森林技術総合センター龍郷駐在(大島郡龍郷町)にあるリュウキュウマツ精英樹採種園と、奄美大島・徳之島に散在する国有林等から採取を行い、精選した種子を林木育種センター(茨城県日立市)に送付し保存しています。
 |
 |
| 奄美群島におけるマツノザイセンチュウ等による リュウキュウマツの被害状況 |
国指定天然記念物に指定されている「五枝の松」 (沖縄県島尻郡久米島町) |
通常の採取は、高枝切りバサミと測桿鎌を用い球果採取しますが、鹿児島県森林技術総合センター龍郷駐在に保存してあるリュウキュウマツについては平均樹高が13mと高く球果採取が容易でないため高所作業車を使用して球果採取を行いました。
これまでに採取したリュウキュウマツの球果は表-3のとおりです。
| 年 度 | 採取個体数 | 備 考 |
| H20 | 4 | 鹿児島県森林技術総合センター龍郷駐在で採取 |
| H21 | 20 | 鹿児島県森林技術総合センター龍郷駐在で採取 |
| H22 | 20 | 徳之島国有林内で採取 |
| H23 | 39 | 徳之島国有林内で採取 |
| H2 | 25 | 鹿児島県森林技術総合センター龍郷駐在で13系統 奄美大島の国有林で12系統採取 |
| 計 | 108 |
 |
 |
| 徳之島の国有林内からリュウキュウマツの球果を採取 | 鹿児島県森林技術総合センター龍郷駐在内から リュウキュウマツの球果を採取 |
 |
 |
| 採取したリュウキュウマツ球果の乾燥 | 精選したリュウキュウマツの種子 |
5.おわりに
平成20年度から奄美群島や沖縄本島で甚大な被害を受けているリュウキュウマツ等の遺伝子を後世に残すため、収集・増殖・保存に取り組んでいますが、今後も関係機関の御協力を得ながら利用上の重要度や保存の必要性、優先度を勘案しつつ、多様な林木遺伝資源を探索・収集し、保存して後世へ継承するとともに、利用しやすくするための特性評価にも取り組んでいきたいと思います。
最後に、リュウキュウマツ等の球果採取にあたり、多大な御理解と御協力をいただきました鹿児島県森林技術総合センター、鹿児島森林管理署、奄美の自然を考える会等の関係各位に対し、心より御礼申し上げます。
参考文献
鹿児島県環境生活部環境保全課:鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物 植物編-鹿児島県レッドデータブック(鹿児島県ホームページへリンク)- 2005
環境省:環境省レッドリストホームページ(外部サイトへリンク)
山崎 敬:琉球からのカエデ属の1新種 植物研究雑誌 Journl of Japanese Botany Vol.75 No.5,282-284 2000.10
海洋博覧会記念公園管理財団:沖縄の都市緑化植物図鑑 P231(リュウキュウマツ) 1997
九州森林管理局西表森林環境保全ふれあいセンター:西表島の植物誌 P52(リュウキュウモクセイ)、P64(セイシカ)、P95(リュウキュウマツ) 2010
南海日日新聞2004年9月5日付け記事:新種の奄美大島産クサミズキに「ワダツミノキ」と命名
南海日日新聞2011年5月1日付け記事:松くい虫被害が拡大-瀬戸内町
南海日日新聞2011年8月9日付け記事:立ち枯れ「西郷松」伐採へ-龍郷町
南海日日新聞2011年9月16日付け記事:シーズン前に松くい虫駆除研修会-奄美市
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.