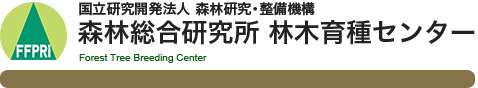ホーム > 業務紹介 > 遺伝資源の収集・保存・配布 > 林木遺伝資源連絡会 > 林木遺伝資源連絡会誌【2018 No.1】
更新日:2025年12月19日
ここから本文です。
八重山諸島の希少樹種
| 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター |
| 西表熱帯林育種技術園 熱帯林育種技術研究室長 楠城時彦 |
1.はじめに
亜熱帯海洋性気候の八重山諸島は,琉球列島の最南部に位置する日本で最も温暖な地域です。30 余りの島嶼群からなる本諸島では,造礁サンゴに縁どられた海岸,マングローブにおおわれた河岸や海岸(写真-1),フクギと石垣に囲まれた昔ながらの家並み(写真-2),サトウキビ畑や牧草地など南西諸島特有の景観が見られます。また,山岳を有する石垣島,西表島と与那国島には,常緑広葉樹林や照葉樹林が広がり,多種多様な動植物が生息します。これらの島々は,世界的な生物多様性ホットスポットとなっており,年間を通して国内外から多くの研究者,自然愛好家や観光客が訪れます。このように,八重山諸島の動植物は,遺伝資源としてだけでなく観光資源としてもたいへん重要です。
八重山諸島は陸橋島嶼群であるため,海洋島の小笠原諸島と比較すると固有種が少ないものの,絶滅が危惧される維管束植物が木本植物を含めて数多く自生しています。とりわけ豊かな植物相をもつ石垣島や西表島には,多くの希少樹種が自生しています。これらの希少樹種の中には,過去に建築材として乱伐されたために絶滅の危機に瀕しているものなど、個体数が激減しているものがあります。当域における希少樹種の保全に資する措置としては,国立公園,生態系保全地域や天然記念物の指定が行われるとともに,定期的なモニタリングや外来種の駆除などが続けられています。
なお,本稿でご紹介する事例やデータの詳細については,拙著「希少樹種講座6:八重山諸島の希少樹種の保全(2015,樹木医学研究 19: 205-211)」をご参照頂ければ幸いです。
  |
| 写真-1 西表島のマングローブ林 |
 |
| 写真-2 竹富島の集落 |
2.八重山諸島の希少樹種
環境省が公表した第4次レッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)によると,絶滅危惧IA 類(CR),IB 類(EN),II 類(VU),準絶滅危惧(NT)いずれかのカテゴリーに該当する希少樹種は八重山諸島全体で合計55 種であり,その大半が石垣島と西表島に生育するものです。絶滅のおそれの高いIA 類に属する樹種には,陸生ではタシロマメ(Intsia bijuga),トゲミノイヌチシャ(Cordia cumingiana),ヤエヤマハマゴウ(Vitexbicolor)などが,マングローブではニッパヤシ(Nypa fruticans)やヒルギモドキ(Lumnitzera racemosa)などがあります。タシロマメは,別名でタイヘイヨウテツボク(太平洋鉄木)と呼ばれるとおり材が非常に堅くシロアリによる食害に強いことから,琉球地方では昔から用材としてよく使われたため伐採が進んでおり自生個体数がかなり少ない樹種です(写真-3左)。トゲミノイヌチシャは,自生個体数が極めて少ない樹種であり,林床に稚樹が見当たらないこともあり絶滅が強く危惧されます。種子が非常に硬質で高耐候性の内果皮に覆われているのが特徴であり,内果皮を物理的に破壊しないと吸水が行われず発芽しません。人工的に発芽させた実生苗の成長を網室内で観察すると,発芽後数カ月で苗高1m くらいまで一気に伸長成長し,その後本葉をほとんど脱落させて成長が停止してしまい枯死したような状態になっています。本種は,生育地でどのように成木になり更新しているのかたいへん興味深い樹種です。ヤエヤマハマゴウは,クマツヅラ科の常緑低木であり,西表島船浮地区の港近くの自生個体は,「船浮のヤエヤマハマゴウ」として沖縄県指定の天然記念物となっています。花序あたりの果実数が100 個以上と多産な樹種ですが(写真-3右),自生木の林床には幼苗がほとんどなく,実験室でおこなった発芽試験では発芽率が0%でした。発芽率の極端な低さが本種の個体数の少なさの原因だと思われますが,不規則な開花・結実や発芽に必要な環境因子など不明な点の多い樹種です。ニッパヤシは,東南アジアやミクロネシアではよく見られますが,日本では西表島のみに自生します。西表島船浦湾ヤシミナト川の自生地である本種群落は,国指定特別天然記念物国内希少野生動植物種であり、林野庁(九州森林管理局)の「船浦ニッパヤシ植物群落保護林」として保護管理が行われています。ヒルギモドキは,西表島に自生するマングローブ構成樹種の1つであり,同島のマングローブでは一番自生個体数の少ない樹種です。多肉質の等面葉をもち,総状花序で小さな白い花をつけます(写真-4)。西表島では,他のマングローブ樹種群落と孤立して比較的陸部に群落を作ることが多い樹種です。
以上の例は,環境省のレッドリストにIA 類(CR)として掲載された樹種の一部ですが,これらの樹種のうちヤエヤマハマゴウとヒルギモドキは,沖縄県が独自に作成したレッドデータブックではIA 類(CR)ではなくII 類(VU)としてカテゴライズされています。また,絶滅危惧種のリストは定期的に更新されており,例えばマングローブ樹種のヒルギダマシ(Avicennia marina)は,環境省の前回のリストではIB 類(EN)とされていましたが現在はII 類(VU)となっています。このような特定の樹種についてのカテゴリー(ランク)の変動は,例えば西表島におけるマングローブ植生面積の漸増といった対象種の実際の消長を反映している場合と,調査者による見落としなどのヒューマンエラーが起因する場合があると思います。潮間帯や陸域の林縁部など比較的簡単に定期的・網羅的なモニタリングが可能なエリアと,道なき道をたどって行かなければいけない山奥部では調査の精度と網羅性が大きく異なるからです。今後,より正確なリスト作りを目指すためには,研究機関から民間企業あるいは個人にいたるまでさまざまなレベルで散在する情報を集積するとともに,情報の統括的な再検証をおこなうことが必要でしょう。また,具体的な調査作業においては,日進月歩での進化が著しいUAV 技術の導入なども有効だと思われます。
  |
| 写真-3 タシロマメの花(左)とヤエヤマハマゴウの果実(右) |
 |
| 写真-4 ヒルギモドキの葉と花 |
3.希少樹種の保全
希少樹種を守るために最も重要なのは,自生個体や群落の保護と生育地の環境保全です。そのため,国や地方自治体は法令に基づいてさまざまな保全・保護区指定や天然記念物指定などを行っています。八重山諸島の希少樹種の保全に資する指定としては,西表島森林生態系保護地域,西表石垣国立公園,船浦ニッパヤシ植物群落保護林,石垣市希少野生動植物保全種及び保護地区,国指定天然記念物「平久保のヤエヤマシタン」,沖縄県指定天然記念物「船浮のヤエヤマハマゴウ」などがあります。林野庁,環境省や地方自治体は,これらの指定対象について分布情報の収集や生育状況の調査によって希少樹種の保全に努めています。また,在来希少樹種の生育環境の保全にとって,外来種による影響の排除も不可欠です。八重山諸島では,過去に飼料や緑化木として人間が導入したギンネム(Leucaenaleucocephala),ソウシジュ(Acacia confusa)やモクマオウ(Casuarina equisetifolia)等の外来樹種が定着しています。希少樹種を含む野生生物種の多様性を保全するためには,繁殖力旺盛な侵略的外来種の定期的なモニタリングや効果的な駆除などを継続しておこなわなければいけません。西表島では,林野庁がギンネム,ソウシジュとモクマオウの分布調査を行っており,ギンネムについては駆除試験を進めています。また,環境省はパンフレットを配布するなど八重山諸島の外来種に関する普及啓発活動をおこなっています。
4.開花・結実フェノロジーの解明に向けて
八重山諸島の樹木の開花・結実フェノロジーは,ほとんど未知の領域であると言っても過言ではありません。希少樹種の着花や結実の状況を野外で調査する場合,野帳,図鑑などの文献,植物に詳しい地元の方の話やインターネットの情報を参考にして現場に出向くわけですが,既存の情報とは異なるケースつまり例外の多さには驚かされます。例えば海岸近くに生育する絶滅危惧IB 類(EN)のイソフジ(Sophora tomentosa)は,植物図鑑「日本の野生植物 木本Ⅰ(1989,佐竹ら,平凡社)」によると開花期が8~12 月となっていますが,西表島や竹富島では春にも着花個体が散見されます。郷土樹種も同様で,防風林や用材として重要な林木であるテリハボク(Calophyllum inophyllum)は,同図鑑では開花時期が夏とされていますが,ほぼ一年を通して着花木を見ることができます。このような例は枚挙にいとまがなく,琉球列島の植物について網羅的に記述したバイブル的な文献である「琉球植物誌(1975,初島,沖縄生物教育研究会)」では,開花・結実フェノロジーに関する記述を敢えて避けているように思えるほどです。もとより,熱帯や亜熱帯の植物は周年開花性を示すものが多く,加えて台風の常襲地域である八重山諸島では強風や潮害によって生殖器官が壊滅的なダメージを受けることがあるため,当域に自生する多くの樹種については,遺伝的に制御される平均的な開花や結実のタイミングを短期間で正確に把握することが極めて困難です。希少樹種の保全や増殖を考える上で,開花・結実フェノロジーの理解が不可欠であり,長期間にわたって根気強く情報を蓄積することが必要です。
希少樹種の保全を考える上で,生息域内外における遺伝資源保全を目指した増殖技術の開発が必要となります。八重山諸島の希少樹種は34 科におよび,樹種により形態,繁殖様式や開花・結実フェノロジーが大きく異なるため全樹種を対象とする増殖体系の確立は困難です。西表熱帯林育種技術園ではこれまでに,30 種近くの希少樹種について収集・増殖・保存を試みました。各樹種について,採種,採穂もしくは掘り取りにより自生地等から収集し,一部については系統管理を行った上で園内の網室や圃場等で保存しています。また当園では,西表島や石垣島に自生する希少樹種の保全や増殖のための知見を収集することを目的として,いくつかの樹種について生育状況を調査するとともに果実と種子の特性に関する研究を行っており、今後も引き続き調査研究を行っていきます。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.