ここから本文です。
研究情報 No.64 (May 2002)
巻頭言
観測65年目を迎えた竜の口山量水試験地
大気-森林系担当チーム長 後藤義明
竜の口山量水試験地は、岡山県の南部、旭川下流左岸の沖積平野に続く丘陵地にあります。この試験地が設置されたのは1937年のことで、森林総合研究所関西支所が創立されたのが1947年ですから、それより10年も前につくられたことになります。この試験地で、森林と水流出の関係を明らかにするためのデータが収集されるようになってから、既に65年が経過しました。
そもそもこの試験地が設置されるきっかけとなったのは、昭和初期に岡山県南部地方で頻発した、ため池の水不足をめぐって繰り広げられた論争でした。この試験地の位置する瀬戸内海沿岸地方では、水不足が深刻な問題であり、渇水対策が緊急の課題となっていました。1933年の同地方は例年にない少雨に見舞われ、ため池の水不足が各地で発生するという異常事態となりました。従来からこの地方の人たちは、森林は水源を枯渇させるものだと信じており、これを契機に多くの人たちが、ため池に注ぐ集水地の森林伐採を希望し、そのために保安林解除を願い出る人が続出するという事態になりました。この水不足の原因をめぐり、農林省林業試験場(現森林総合研究所)の平田徳太郎博士と岡山県林務課の山本徳三郎技師の問で、流域のアカマツ林の影響が論じられたのです。現地調査をした平田博士は、ため池が満水するかしないかは雨の降り方によるものであり、森林の影響はわずかなもので森林の伐採では解決できない、というものでした。これに対し山本技師は、岡山県南部地方のような少雨地方では、ため池の水確保に水源かん養林は効力を持たず、かえって水源を枯渇させるものだと主張しました。
3年間におよぶこの論争は、結局決着を見ることはありませんでしたが、平田博士の提言に従い、当時の山林局(現森林管理局)は岡山市郊外の国有林に試験地を設け、森林伐採による流量変化を調べる研究に着手しました。これが1937年のことで、こうして竜の口山量水試験地が誕生したのです。以来、わが国の少雨地域を代表する試験流域のひとつとして、今日まで60年以上にわたり降水量および流域の水流出量が継続して測定されています。こうした長期間にわたる観測試験の結果、森林の持つ水源かん養機能の実態がさまざまに解明されてきました。ここで紹介した平田博士と山本技師の双方の主張についても、その正当性や誤謬と考えられる点が明らかにされてきたのです。
近年、西日本を中心として、日本中の各地で毎年のように水不足の騒ぎが起きています。森林の水源かん養機能の高度発揮と、その維持増進技術の開発が求められています。さらに最近では地球温暖化等の気候変動が懸念されており、人類活動による気候変化が森林の持つ水源かん養機能へ及ぼす影響が心配されています。このような気候変動の影響などの解析には、長期間の観測データが不可欠であり、量水試験地の重要性は薄れることはないでしょう。今後も、少雨地帯の森林の持つ水源かん養機能を解明するためのモニタリングステーションとしての機能を果たすべく、竜の口山量水試験地での観測を継続していきます。
研究紹介
鼠の唾を集める
島田卓哉 (生物多様性研究グループ)
量の少ないものの例えとして「蚊の涙」という言葉があります。「鼠の唾」という慣用句はありませんが、蚊の涙には負けるものの、これも量の少なさを表現するにはなかなかいい言葉のように思います。あまり自慢できる話ではないかも知れませんが、私はネズミの唾液を集めることに関しては日本一だと思っています。そこで今回は、ネズミの唾液の取り方についてお話します。
そもそもなぜネズミの唾液を採集する必要があるのでしょうか。アカネズミは、北海道から九州の山林に広く分布する体長10cmほどの野ネズミで、植物の種子や無脊椎動物を主な餌としています。なかでもドングリ(コナラ属樹木の種子)は秋から越冬時期の重要な餌です。アカネズミはドングリを集め、土の中に埋めて保存し(貯食)、再び回収して利用しますが、回収されなかったドングリは母樹から離れた場所で発芽することができます。このように、アカネズミはドングリの捕食者であるだけでなく、重要な種子散布者としても働いていると考えられています。
ところが、ある種のドングリには多量のタンニンが含まれています。タンニンは植物によって生成される毒物の一種で、タンパク質と結合して消化阻害を起こすほかにも、消化管の組織を損傷したり、体内ナトリウムバランスを撹乱したりする作用を持っています。このようなタンニンが、乾量比にして、コナラには3%程度、ミズナラには実に9%も含まれています。タンニンに対抗するために、一部の哺乳類は、唾液中にタンニン結合性唾液タンパク質(PRP,Proline-Rich Protein)を分泌することが知られています。このタンパク質は、タンニンと非常に強い結合力を持っており、タンニンが体内に入り悪さをする前にブロックする役割を持っています。アカネズミがPRPを持っているかどうか、それを確かめるために唾液の採取を計画しました。
唾液をとるためには、まずネズミを麻酔する必要があります(写真-1)。いろいろと試してみましたが、麻酔の種類は、ケタミンとキシラジンの混合液が麻酔に入る時間が短く覚醒も早いため、もっとも適しているようです。続いて、カルバコールという薬品を投与します。この薬品は、唾液の分泌を促す働きを持っており、カルバコールなしでは分析に十分な量の唾液を採取できません。はじめの頃は、この薬品のことを知らず、苦労しました。ある文献には、白熱電球にネズミを30分間さらすと唾液がよく出るようになると記されていましたので、早速試してみましたが、効果はさっぱりでした。
あとは、分泌された唾液を順次ピペットで採取してやればいいのですが、ここでも一つ工夫が必要です。麻酔されていても動物は呼吸をしていますので、分泌された唾液が気管に詰まり窒息してしまうという事故が頻発しました。そこで、傾斜をつけた保定台を用意し(写真-2)、唾液が気管に流入しないようにしました。残った唾液で窒息しないように、唾液の分泌が収束するまで(15分程度)、唾液の採取を続けます。こうして採取された唾液が写真-3です。平均して0.4ml程度の唾液を採取することが可能です。
採取された唾液を分析したところ、アカネズミもPRPを分泌していることが明らかになりました。今後は、PRPの測定を通じて、アカネズミがタンニンに対してどのように対処しているのかを明らかにしていきたいと考えています。

写真-1: アカネズミへの麻酔投与

写真-2: 保定して唾液の採取を行っている
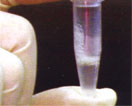
写真-3: 採取された唾液
シカが土壌の養分状態を変える?
古澤仁美 (森林環境研究グループ)
通常、森林では牧場のような高い密度で大形の草食動物が生息することはありません。ですから、森林で養分の循環を考えるうえでは草食動物の活動の影響は無視できると考えられてきました。しかし近年、日本全国でニホンジカの数の増加が報告されています。奈良県と三重県の県境にある大台ヶ原山もニホンジカの個体数が17.5~30.9頭/km2と高いことで知られています。大台ヶ原の林床に優占するミヤコザサは本来90cm~100cmの高さになる植物ですが、10cm位の高さで一面に刈り込まれたようになっています(写真-1)。これはニホンジカがミヤコザサを餌にしているためです。このように森林の様子を変えるほどニホンジカが増えてきたとき、土壌の養分状態は変わるでしょうか?
ミヤコザサ(以下ササといいます)はその年に成長した地上部が翌年の秋までに枯れる一年半生の植物ですので毎年たくさんの養分を吸収し、枯れて有機物を土壌へ供給します。ササがあればあるほど、土壌とササの間で循環する養分量が大きくなります。それに対し、ニホンジカはササの現存量を減らして循環する養分量を少なくします。これはニホンジカが養分状態に与える間接的な効果ですが、大台ヶ原のようにたくさんササが食べられている場合には影響が大きいのではないかと予想されます。そこで、シカ柵で囲って入れないようにする(シカ除去区)と自由に入れる(シカあり区)、ササを刈り取る(ササ刈り区)と刈り取らない(ササあり区)を組み合わせた処理区を作って、土壌中の養分濃度を調べることにしました。シカあり・ササあり区が現在の大台ヶ原の状態(対照区)です。ササ刈り処理は、今よりササが少なくなった状態を実験的に作ってみたものです。実験を開始したのは1997年の春です。実験開始後、毎年秋にササの現存量と土壌中の水溶性の養分濃度を調べました。
シカ除去ササあり区ではシカに食べられなくなったので、1997年秋の地上部現存量は対照区より多くなりました。その後も、毎年生えてくるササの高さが年々高くなった結果、4年後の地上部現存量は対照区の4倍以上に増加しています。逆にシカあり・ササ刈り区では、毎年春にササ刈りを続けていることで対照区より現存量が少なくなっています。また、シカ除去・ササ刈り区ではササを刈るもののシカに食べられないのでササの現存量は対照区よりやや少ない程度です。
一方、土壌中の水溶性の養分濃度はササ刈り処理による影響を受けることが分かりました。亜硝酸、硝酸、カルシウム、マグネシウム濃度は、ササ刈りをした方がササありより高いことが認められました。ササ刈りをすることでササの現存量が少なくなり、ササによる養分吸収が少なくなるために土壌中の水溶性養分濃度が増加したと考えられます。一方、カルシウム、マグネシウム濃度はシカ処理でも差が認められ、シカありの方がシカ除去より高かったです。シカがササ刈り処理と同様に、ササの現存量を少なくしてササによる養分吸収を少なくするためと考えられます。このことから、シカはササの現存量を変えることで、間接的に土壌中の水溶性養分に影響を与えることが明らかになりました。
シカが土壌に与える影響については他にもいろいろあります。例えば、フンや尿が土壌へ与える影響や、ササを食べることで地表の被覆が減少するので土壌の移動が大きくなるのではないかといった点については今後明らかにするつもりです。

写真-1: 試験地の様子
林床の植物はほとんどササですが、シカに食べられているのでとても見通しがよい。奥に見えるのが処理区。
連載
関西地域の森林土壌 (1)
褐色森林土
森林環境研究グループ 金子真司
我が国は地形が急峻で平野が少なく、温暖・多雨の島国です。我が国固有の風土は土壌にも大きな影響を与えています。日本の土壌図を眺めると、褐色森林土の分布が広いことがわかります。褐色森林土は森林下にできる有機物の蓄積した黒色の表層(A層)と褐色の下層(B層)からなる土壌で、温帯から暖帯の山地に分布し、性質は変化に富んでいます。褐色森林土は林野土壌の分類(1975)では8亜群に分けられます。そのうち褐色森林土亜群が標準的で、大半はこの亜群の土壌です。褐色森林土亜群はさらに次の6土壌型と1土壌亜型に分類されます。
- 褐色森林土亜群の土壌型
- 乾性褐色森林土(細粒状構造型): BA
- 乾性褐色森林土(粒状堅果状構造型): BB
- 弱乾性褐色森林土: BC
- 適潤性褐色森林土: BD
- 弱湿性褐色森林土: BE
- 湿性褐色森林土: BF
- 褐色森林土亜群の土壌亜型
- 適潤性褐色森林土(偏乾亜型): BD(d)
乾性型の褐色森林土は尾根に近いところに、また湿性型は谷に近いところに主に分布しますが、谷に近くても風の通り道のような場所では乾性型が出現することがあります。ところで褐色森林土は、最近の国際的な土壌分類では、やや未熟な土壌のカンビソル(WRB:世界土壌照合基準)あるいはインセプティソル(U.S. Soil Taxonomy)に分類されます。褐色森林土がやや未熟であると判断される理由は、土壌中に粘土集積層をもたないからです。世界的にはなだらかな地形が広がる地域が多く、一般に表層から粘土が溶脱して下層に集積した土壌が分布します。それに対して、我が国の山地は地形が急峻で雨が多いために土壌が移動しやすく粘土集積層が形成されないと考えられています。なお、今回から4回にわたり関西地域に出現する森林土壌を紹介する予定です。

写真-1: 我が国の代表的森林土壌である「褐色森林土」
おしらせ
関西支所ホームページによる「所内樹木園のご紹介」
関西支所のWWWホームページにて「所内樹木園のご紹介」を行っています。
所内地図や五十音順の樹種名から簡単に検索が可能です。クリックすることで画像や説明も表示されますので、どうぞご利用下さい。
URL http://www.fsm.affrc.go.jp/
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.
