ダイバーシティ推進室 > 知る > 外部機関でのシンポジウム・セミナー > 「GenderSummit10-AsiaPacific2017」参加報告
更新日:2017年9月28日
ここから本文です。
「GenderSummit10-AsiaPacific2017」参加報告
-
-
- 主催
- 参加者
Gender SummitはEUが中心となって2011年に始まった会議
5月25、26日に一橋講堂で開催された「Gender Summit 10-Asia Pacific 2017」に参加しました。Gender SummitはEUが中心となって2011年に始まった会議であり、アジアでの開催は2015年に第6回がソウルで開催されて以来になります。今回の会議は、4つのPlenary sessionと6つのParallel sessionから構成されていました。Plenary session 1以外は、スピーカーの講演とパネルディスカッションという形式でした。開会式ではヨルダン王女や文部科学副大臣がゲストとしてスピーチされるなど、重要な会議であることがうかがえました。
Plenary session 1「History and Future of Gender and Diversity」
Plenary session 1「History and Future of Gender and Diversity」はゲストスピーカーの基調講演で、IBMの浅川智恵子氏、香港大学のAngela Ki Che Leung氏、京都大学総長の山極壽一氏が講演され、講演者の順に未来から原始に歴史を遡るという構成でした。個々のお話は初めて聞く話題ばかりで非常に興味深いものでした。浅川氏は14歳で全盲になられた後、情報収集と移動に不便を感じ、それを克服するために画像認識や音声認識とAIを組み合わせた全盲の方のAccessibilityを補完するデバイスを開発されました。こういった機器は全盲の方のみではなく、健常者にも応用可能なものであり、ダイバーシティがイノベーションを生むという実例であると述べられました。Leung氏は東アジアの国々における儒教と男女平等についてお話しされました。中国における纏足や助産師における女子えい児殺しなど、歴史的に行われた事例が儒教の考えに基づいていた可能性もあるということ、しかし、儒教の考えは父系中心の考えではあるが、男女の不平等を押しつけるものではないと言う結論でした。非常にデリケートで難しいお話しでしたが、納得させられる部分もありました。しかし、同時通訳を聞いても理解できない部分もありました。山極氏は人類の進化とGender equalityという内容で、人間や類人猿の身体的特徴や発達段階、生活様式など様々なデータを元にお話しをされました。人類は、ゴリラやチンパンジーと同じヒト科に属しますが、他よりも早く離乳し、他にはない幼児期と青年期があるということ、また、人類の家族は森林から出たことで外敵にさらされ、出産後の子育てが困難になり、Communityで子育するようになったため、生物学的な近親というのはあまり意味がなかったのではないかという結論を述べられた。
Plenary session 2「Female Researchers Tackling Global Issues」
Plenary session 2 「Female Researchers Tackling Global Issues」は、発展途上国の女性研究者や技術者の状況について話し合われました。インドの地下鉄建設の現場で唯一の女性エンジニアとして労働者を束ねている阿部玲子氏は印象的でした。日本では労働基準法でトンネルや鉱山など坑内での女性の労働が禁じられていたほか、女性が山に入ると事故が起こるというような古い風習や信仰があり、阿部氏は日本ではトンネル工事に従事することができませんでした。そこで、ノルウェーに留学し、トンネル技術を勉強した後、台湾高速鉄道のトンネル工事に従事することができましたが、やはり日本ではトンネル工事をさせてもらえず、会社を退職して、現在は、建設コンサルタントとして発展途上国の鉄道建設に従事されています。クレーンが倒れても「No problem !!!」と言っているようなお国柄であるインドの地下鉄建設現場においての安全対策を、女性ならではの細やかな視点で改善していったエピソードは、非常に興味深いものでした。
Parallel session 1「Benefits from Women’s Participation in Science、 Technology and Innovation」
Parallel session 1「Benefits from Women’s Participation in Science、Technology and Innovation」では、企業、大学、政府の女性の視点を取り入れた取組事例の紹介とパネルディスカッションが行われました。日産自動車の報告の中で、調査で家庭における自動車購入決定権は多くの場合女性にあることが分かり、開発や販売の現場に女性の視点を取り入れたことで利益が上がり、利益が上がったことで、女性の視点の重要性を会社全体として共有できたという報告がありました。これは、Diversity(多様性)の視点がもたらすInnovation(革新)が、さらに企業や社会にInclusion(受け入れられる)ことが大切であるという一例です。それにより各個人は個性が尊重されていると感じ、社会や企業の中で居心地の良さを感じるそうです。これからは様々な社会の中でこのInclusionの取組がさらに重要になるとのことでした。
Tokyo Recommendation BRIDGE
会議の最後に、まとめとしてTokyo Recommendation BRIDGEが読み上げられました。“BRIDGE”つまり架け橋という意味です。具体的には、1.Bridges Gender and STI(ジェンダーと科学・技術・革新との架け橋)、2.Bridges SDGs(国連が掲げる持続的可能な開発目標(http://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/15775/参照)の架け橋)、3.Bridges all people(全ての人々の架け橋)です。ちなみにGender Summit 11は今年の11月にカナダのモントリオールで開催されるということでした。私自身、このような国際会議に参加したのは初めてでした。話題の内容も多様で初めて聞くことが少し疲れましたが、また機会があれば参加したいと思います。勉強になった2日間でした。
ダイバーシティ推進室長 安部 久:記
 |
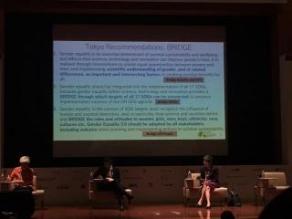 |
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.
