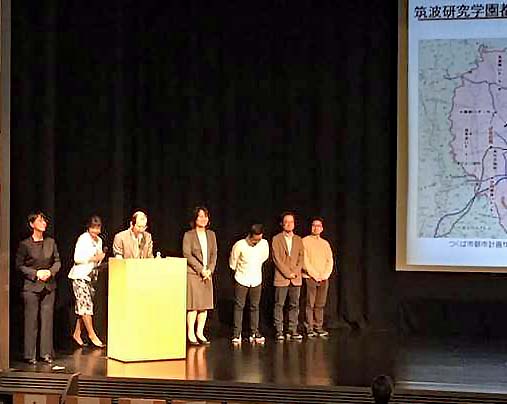ダイバーシティ推進室 > シンポジウム・セミナー参加報告 > つくば市男女共同参画フォーラム「つくばミンナのつどい2018」参加報告
更新日:2021年3月10日
ここから本文です。
つくば市男女共同参画フォーラム「つくばミンナのつどい2018」参加報告
- 日時:2018年12月01日(土曜日)
- 場所 : つくばカピオ(茨城県つくば市竹園1丁目10-1)
- 主催 : つくば市
- 参加者 : ダイバーシティ推進室長 髙山 範理、構造利用研究領域 宇京 斉一郎
プログラム
- オープニング
- 主催者挨拶
- 第13回男女共同参画推進標語「愛ことば」展示・表彰式
- 講演 東京大学 瀬地山 角氏 による「笑って考える男女共同参画 男の家事が社会を救う!」
- 男女共同参画推進団体による活動状況紹介
- 交流タイム(男女共同参画推進団体によるパネル展示)
参加報告
つくば市男女共同参画フォーラムはつくば市の主催で毎年開催されており、今年で13回目の開催です。男女共同参画に関する講演を中心として、男女共同参画標語「愛ことば」の表彰式や、つくば市で活動する団体による活動状況の紹介が行われます。ダイバーシティ推進室では、つくばの研究教育機関の一員として、研究所の活動状況の紹介およびパネル展示を行いました。
今年の講演会の講師の紹介には、日本テレビ「世界一受けたい授業」の東大生100人へのアンケートで東大の人気No.1に選ばれた講義をされているとのこと。NPO法人として保育所も運営されて、自身も二人の子の保育園への送迎を10年間担われて、おまけに「笑って考える」とまであります。
こちらも「ほんまかいな?」と、多少身構えながら聞き始めましたが、ご本人が主張されるところの標準語である関西弁による軽妙な語りと、ときおり放たれる強いメッセージにぐいぐいと引き込まれる1時間30分(1コマ)となりました。
配偶者控除について
所得水準の高い首都圏のほうが、妻の有業率が低いデータを示され、夫の収入のみで成り立つような家計を優遇している可能性があることが示されます。特段、夫の収入が高くなくても、育児とフルタイム労働が【両立】しない職場環境がまだまだ日本には多く、やむなく職を離れる女性も多数存在しているのでは?とも思いましたが、この違和感に対する、先生の答えは「夫がもっと家事・育児をして妻をもっとアシストし、家庭責任を妻だけに押しつけないこと!」ということなのかもしれません。ちなみに、両立という言葉に【 】をつけたのは、瀬地山先生が嫌いな言葉としてあげられていたからです。家庭と仕事という文脈で用いられるとき、この言葉自体にバイアスが潜んでいる。ということだと思います。
外部不経済としての家事・育児
植林をする林業者VS植林をしない林業者は、産出される木材の材質が同じで、買い手に植林の有無が見えない場合、後者が有利となり、結果、荒廃した山が増えてしまう。という少し目が覚める例を挙げられ、同じように、子育てをする社員VS子育てをしない社員であれば、労働市場では後者が有利となり、子育てコストは払われないため、全体として社会は少子化へと進む、と説かれます。対策として必要なことは、外部不経済(子育てコスト)を内部化することだと説かれます。女性社員だけでなく男性社員の背後にも育児・介護はあり、そのコストを個人にのみ負担させるのはもはや無理であると。この分析は鋭く、植林という例の効果も相まって、大変印象に残りました。
テレビにあふれるジェンダー論的にNGなCM
某調味料メーカーや栄養ドリンクのCMを紹介され、女性に過剰に家庭の役割を負わせた描き方や、企業戦士として働くかわいそうな夫の像に、ジェンダー論の観点から鋭い「つっこみ」を先生が入れ、会場は大いに盛り上がります。先生のつっこみがなければ、私などは普通に受け入れて見ていたCMでしたので、視点を変えるとかくも違うのかと、大変驚きでした。
必ず「たからくじ」を当てる方法
平均的な世帯では、夫が残業代で稼ぐよりも、妻が外に出て働くほうがコストパフォーマンスは高い。妻の生涯賃金を「宝くじ」とみたて、それを現金化するためには、夫が家事をして妻の就業を助けたほうが良いと説かれます。
そこで、こんな数字も登場します【49分 VS 3時間45分】
これは、6才未満の子供がいる世帯の育児時間の統計です(総務省「社会生活基本調査」 2016年)。どちらが夫で、どちらが妻かは言わずもがなではないでしょうか。
「たからくじ」を確実に得ることができるのが明白なのに、上記の育児時間の数字はおかしい、というわけです。何も言えません。
男の家事が「男」社会を救う?
ここまでは、経済的な切り口でのお話。最後のほうに、男性の過労による自殺が多い実態が紹介されます。男性が家事を行うことは、女性の就労を支えるだけでなく、家庭で過ごす時間が増え、ひいては男性自身を救うことになる、と説かれます。講演タイトルの「男の家事が社会を救う」の、社会とは、男性が中心として築いてきた高度成長期に成功したモデルの社会のことであり、講演で先生が一番伝えたかったことは、ここにあるのかもしれないと感じました。平日が難しいなら、週末に、またはノー残業デーに、家事をもっと分担することから始めようと、呼びかけます。
経済や、社会政策、ご専門のジェンダー論や社会学など、まさに大学の白熱講義を体験し、学びを経て、いろいろと考えはじめている自分に気づきました。
研究機関に向けて
講演終了後、瀬地山先生には男女共同参画推進団体の活動状況紹介も見ていただき、我々、研究機関へは、以下のようなコメントをいただきました。テニュア職を得る30代で、多くの女性は出産というライフイベントがあり、男性とキャリアパスが異なるため、業績をポイントの積み上げで評価すべきではない。例えば、40代で初めてテニュア職に応募してくる女性を排除してはいけない、とのアドバイスをいただきました。
ダイバーシティ推進室 併任 構造利用研究領域 宇京 斉一郎:記
|
壇上での5研究機関合同プレゼンテーション
研究所のダイバーシティ推進の取り組みについて紹介しました |
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.