ダイバーシティ推進室 > 知る > ダイバーシティ推進セミナー > 第22回エンカレッジ推進セミナー
更新日:2025年11月6日
ここから本文です。
第22回エンカレッジ推進セミナー
「田辺鶴瑛の介護講談」DVD上映会開催報告
このセミナーはTV会議にして支所等に中継し、 |
|
プログラム
- 桂川理事挨拶
- 「田辺鶴瑛の介護講談」上映
上映概要
2016年3月に浪曲寄席 木馬亭にて収録された、講談師、田辺鶴瑛さんの介護講談のDVD上映会を行いました。実母、義母、義父の3人の介護をやり遂げた鶴瑛さんが、義父の看取りの際、「介護してよかったな~」と思えるに至ったその経緯を、軽妙な講談の語り口で紹介してくださいました。
上映会を終えて
隅から隅までズズ、ズズィ~~ッと! 実母、義母、そして全くもって疎遠だったという義父の介護の完全実話講談。
まずは講談師を目の前にしてポカンとしている聴衆の「講談とはなんぞや? 」という問いに答えるべく、「三方ヶ原軍記」という定番講談が披露されました。あまりの難解さと弾丸トークに、のっけ不安な気持ちを抱いたのはきっと私だけではないはずです。
講談師、田辺鶴瑛さん。「認知症介護の大変さを心配するよりも、実態を知っていた方がいざという時に楽な気持ちになれる。」と、大嫌いだった義父の、つらい・汚い・苦しかった介護を笑いに変えていった経過を披露してくださいました。みなさん最後には、「講談」というものそして「認知症介護」が、それほど難解でもなく、意外と楽しめそうだと感じることができたのではないでしょうか?
さて、その講談のなかには、認知症介護に笑顔を添え、「大嫌い」を「大好き」に変える極意が見られました。
- 認知症カフェの利用
認知症の人とその家族が気軽に利用できる場所だそうです。こちらでは認知症患者との接し方のテクニックを教えてくれたり、介護に関する様々な相談にのってくれます。調べてみましたら、つくば市にもありました(オレンジカフェhttps://www.city.tsukuba.lg.jp/kosodate/koureisha/houkatsu/1001345.html)。 - 一時的に介護施設に預けるなど、国や自治体の制度を大いに利用する
「しっかり完璧に介護をしなければならない」と頑張っていると破たんします。国や自治体の制度を適度に利用し、自分の時間を大切にするべきです。 - 認知症の人を変えることはできない。自分が変われば介護を笑いに変えられる!?
何かしてあげても、良かれと思ってアドバイスしてあげても、認知症の人は覚えていてくれないのでそんな行為は無駄なだけ。できないことを咎めるよりも、できることを褒めるという発想の転換が重要です。また、認知症の人のいうことを受け止めてあげることで、問題行動を起こさなくなることがあるようです。例えば、四六時中「助けてくれ~! 」と叫ばれると、イライラからつい「もう呼ばないで! 」と言ってしまいそうですが、そのような義父に「助けに来たよ」と言ってあげたら「お~助かった! 」と安心してくれたそうです。このように、真面目につきあわず大いにうそをついて褒めておだて、良いところを発見することで、介護する側にも楽しむ余裕が生まれます。 - 思い出話をしてもらったり、歌を歌ってもらう
昔、体験したことを語ったり、好きだった歌を歌うことで幸せを感じてもらうことができるということです。そんな姿をみると認知症を患っていることを忘れてしまうそうです。介護をする側も、心穏やかな楽しい時間を過ごすことができます。
鶴瑛さんは冒頭で、根性の悪い人(ここでは鶴瑛さんの義父)の介護は難しいと言っていましたが、介護に対する発想の転換をすることにより、介護を楽しむ姿勢が生まれ、鶴瑛さんと義父の距離が縮まりました。寝た切り認知症になった義父が亡くなる少し前に「お前は天使のようだ。ありがとう。」と言ってくれたというエピソードを紹介する場面。義父と過ごした時間を愛おしむ鶴瑛さんの優しいまなざしが非常に印象的でした。皆さんの心にも沁みたのではないでしょうか?
野生動物研究領域 鳥獣生態研究室・ダイバーシティ推進室(併任) 永田純子:記
会場の様子




PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.

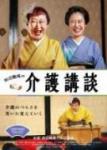 (PDF:41,415KB)
(PDF:41,415KB)