森林総合研究所エンカレッジ推進懇談会
更新日:2016年3月3日
ここから本文です。
森林総合研究所エンカレッジ推進懇談会
国内外の男女共同参画状況を理解するとともに、森林総合研究所の男女共同参画推進のための対策を検討するため、平成24年9月20日に森林総研エンカレッジ推進懇談会を開催しました。
| 日時 | 平成24年9月20日(木曜日) 14時30分~15時30分 |
| 場所 | 本所情報棟森林環境解析展示室 |
開催報告
目的
9月20日に森林総合研究所でエンカレッジ推進懇談会が開催されました。この懇談会は、森林総合研究所役員・幹部が今後の男女共同参画を進めるための対策について話し合うもので、森林総合研究所として初の試みです。エンカレッジ推進本部アドバイザーの原ひろ子先生(城西国際大学客員教授)にもご出席いただきました。
討議方法
和やかに、かつ活発に討議するため、3グループに分かれてグループ討議方式をとりました。最初に原先生、城土理事、古澤男女共同参画室長が話題提供者となり話題を提案し、次に各グループでその話題の中から1つ選んで討議しました。最後に各グループからグループ討議の報告をしていただき、全体討議を行いました。
討議報告
各グループともリラックスした雰囲気で活発に討議が行われました。グループ討議を用いることで、この懇談会が意見交換の場としてうまく機能したと考えられました。今後もこのような意見交換をする機会をつくっていきたいと考えます。以下に各グループの簡単な討議メモを付記します。
Aグループ
「森林総研のみでなく、研究者や職員候補者を育てる当該分野での高校・大学・大学院教育に関する現状と今後の展望は、どのようなものか?」
森林学科となってから、森林・環境・里山といったことに興味を持つ女子学生がふえて、学部における男女の数の差はなくなり、学業成績の差もない。学部で半々いるのに、森林総研に応募する段階では半々にはならないのはどうしてか?
1950年代ごろは、教授が女性を採らないなどの状況もあった。今は、このようなことはないかもしれないが、そもそも男女問わず大学院に進む人が少ない。特に、大学院、博士課程と進むにつれて女性割合は減るので何らかの抑制が働いている。就職してからも、森林総合研究所においては仕組みの上では男女差はないが、女性管理職としてのお手本が無い状況である。管理職候補、あるいは新しく管理職になった職員には男女問わず研修等の充実が必要である。
Bグループ
「”男女共同参画”から”多様性確保”の推進へ」
男女共同参画推進のメリットは、多様な視点を取り入れることによる活性化、幅の広がりにある。多様な視点を持つ組織はタフである。「男女」だけでなく、年齢や、国籍、様々なバックグラウンドを含む多様性が重要である。
男女共同参画推進の目的が形骸化している。数値目標の達成のため、無理矢理男性の育休取得数をふやす、審議会等に無理に女性をいれる、採用に関しても男女同等の能力の場合は女性採用としているが、実質的なものかは難しい。一方、数値目標がなければ、いつまでたっても多様性は確保できないのも事実。
森林総研で、採用割合だけでなく応募割合も30%を達成したのは、男女共同参画事業宣伝の成果で、より優秀な人材が集まったということでメリットであった。ポスドク、任期付きをへての選考採用、採用後も霞ヶ関勤務、管理職(昇進)、海外経験、転勤など、キャリアの道筋は多様になってきた。
女性だけでなく男性についてもロードマップ(産総研のロールモデルのようなもの)を提示してはどうか。キャリアカウンセリングの効果も示せる。森林総研を通り過ぎたあと(異動、退職?)にも、ノウハウを蓄積できるし、去りっぱなしではなくネットワークとして成果の還元になる。
今後は男女共同参画推進から多様性推進・確保を目指したアプローチとしたほうが、男女ともにメリット感がある。
Cグループ
「森林総研のみでなく、研究者や職員候補者を育てる当該分野での高校・大学・大学院教育に関する現状と今後の展望は、どのようなものか?」
森林総研の女性一般職採用については、かつては女性は実家から離れない傾向があったが、現在はそのような問題はほとんどないのではないだろうか?しかし、森林総研職員の採用に関して応募の段階で男女差が大きいのは一般職である。これには、採用予定の確定が遅れ、優秀な候補者(特に女性)は国が先に採用してしまうので、残りの女性候補者がまず少ないという問題がある。また、一般職は採用されるまで森林総研の存在をほとんど知らないようだ。なお、今まで一般職採用は高校卒程度(3.種)を対象としてきたが、現在大学進学率が高く、今後は2.種も対象としてアピールする必要があるだろう。
森林総研の認知度を上げるため、森林総研という職場が「夢のある職場、夢を与えられる職場」であることを、募集段階だけでなく、常日頃から積極的にアピールする必要がある。林野庁ではインターシップを実施しているが、森林総研でもこれらを参考にインターシップの導入を検討したら良いのではないだろうか。
(ここまで男女共同参画室長 古澤 : 記)
(追記)
会の冒頭、理事長が家族責任を理由に米国国務長官補佐を退任したスローター氏について紹介された。非常に特殊な例とはいえ、仕事を続けるためには、さまざまな障害を乗り越える必要があること、その中で家族責任の負担が大きいという点で、共通する問題である。
このような家族責任を持つ人が仕事を続けるためには、たまたま息子がぐれなかったから、たまたま両親が健在だったから、たまたま近所で助けてくれる人がいたから、たまたま同僚が理解してくれたから、そして何より大きいのは、たまたま理解ある上司であったから・・・という多くの幸運を得て、初めて可能となる。この事は多くが指摘することである。
森林総研が「夢のある職場/夢を与えられる職場」であるかどうかを考える時、職場では「理解ある上司」が「たまたま」ではなく「必ず」存在するかどうかが、重要な鍵の一つとなるだろう。
(主任研究員・エンカレッジ推進委員 金指あや子 : 記)
◆会場の様子◆
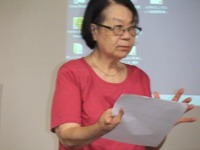



お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.
