ここから本文です。
森林総合研究所関西支所令和4年度公開講演会の開催報告
開催報告
2022年6月11日(土曜日)13時30分より、龍谷大学響都ホール校友会館にて「森林総合研究所関西支所令和4年度公開講演会」を開催しました。この公開講演会は、地域の皆様に森林の不思議さや奥深さを「わかりやすく楽しく」知っていただくことを目標に毎年開催しているものです。
今回のテーマは「外来カミキリムシから花咲く春を護る」と題して、「サクラの花がピンチです」「モモの花がピンチです」「サクラの花を護(まも)るために今できること」の3つの講演により、外来カミキリムシの生態や日本での被害状況、そしてサクラを護る方法など、研究成果の最前線についてお話しいたしました。
新型コロナウイルス感染症対策のため、今年も制約のあるの中での開催となりましたが、このことについてもご理解、ご協力いただき誠にありがとうございました。
来場者の皆様から多くのご質問をいただき、この話題に対する皆さまの関心の高さが伺えました。また、アンケート調査によるご意見は次年度講演会の参考といたします。ご協力ありがとうございました。

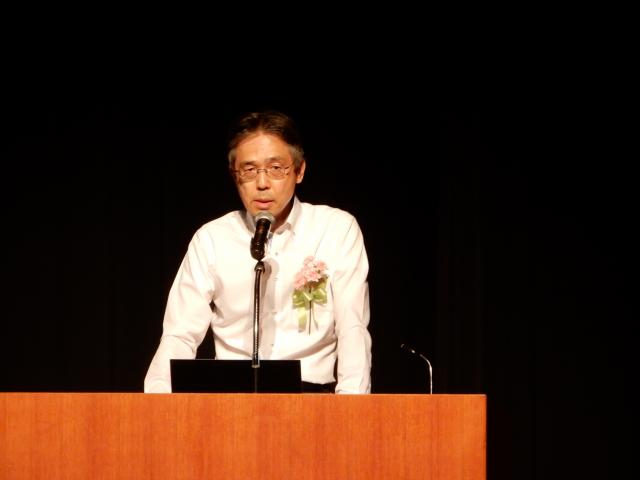


動画公開
講演をYouTubeで公開しています。講演名をクリックすると動画ページに移動します。
講演1.サクラの花がピンチです~外来種クビアカツヤカミキリの生態(森林総合研究所 森林昆虫研究領域昆虫生態研究室長 加賀谷 悦子)
講演2.モモの花がピンチです~サクラとモモから羽化したクビアカツヤカミキリの比較(森林総合研究所関西支所 生物被害研究グループ長 浦野 忠久)
講演3.サクラの花を護(まも)るために今できること~大阪の被害状況と防除対策(大阪府立環境農林水産総合研究所 環境研究部自然環境グループ副主査 山本 優一 氏)
森林総研関西支所の講演会に寄せられた質問と回答
|
|
質問 | 回答 |
| 1 | クビアカツヤカミキリを捕まえてしまったらどうしたらいいですか。 | クビアカツヤカミキリは特定外来生物なので、許可なく動かしたり飼育すると法律違反となる。採取許可を持つ人に渡すか、駆除してください。京都府など、まだ被害が確認されていない都道府県で見つけた場合には、駆除するだけでなく、自治体に報告を(できれば写真付きで)してください。 |
| 2 | エサクラ・モモ以外の木も対象ですか?バラ科だけですか? | クビアカツヤカミキリの被害が確認されているのはバラ科樹木の中でもサクラ亜科、つまりウメ、モモ、サクラ、アンズ、そしてプルーンです。まだ確認されていないオウトウ(サクランボ)も注意が必要です。その他のバラ科樹木に被害は全くでないとは言えません。 |
| 3 | エゴノキがカミキリムシの被害を受けることはありますか。 カリンにはカミキリムシは入るのでしょうか。 |
在来のゴマダラカミキリはいろいろな木を利用することで知られていて、それはエゴノキやカリンも入ることがあります。 |
| 4 | 2011年に埼玉で日本初の発見があったとのことですが、他の11都道府県へは埼玉県から広がったのか、複数の侵入ルートがあったのか知りたいです。 | 全国6カ所の被害地のそれぞれごとに出てくる遺伝子が違っていました。つまり、1回の侵入で各地に広がったのではなく、それぞれの場所に独立して侵入してそこから広がっていると考えられます。2015年に全国各地で被害が見つかった後、新しい被害地は見つかっていません。 |
| 5 | 1本の樹木(樹齢にもよると思いますが)への産卵数は何個ぐらいですか。 | 直接の観察では実証されていないのでお答えしにくいですが、1頭の雌が1000卵以上産卵することもあるので、複数頭の雌がその木にとどまった場合、1000卵以上の産卵があってもおかしくはないと思います。 |
| 6 | 何度も侵入チャンスがあったと思いますが、2011年からというのは何か理由が考えられますか?(原産地での発生が激しかった、など) | 原産地からの物流が急増して、梱包材の移動が増えたことが侵入圧を高めたと考えています。 |
| 7 | 国外からの侵入防止に関する対策が必要かと思われますが、どのようなことが考えられるでしょうか。 | 梱包材は認証されたものしか使えなくなったので、伴う移入種の侵入も少なくなったと考えられますが、今後は木材や木製品の輸入検疫についても何らかの措置が必要になってくると感じています。 |
| 8 | サクラ材の輸入がどのような用途でどの程度あるのか教えてください。 | 床材(フローリング)によく用いられます。 |
| 9 | クビアカツヤカミキリは日本だけでなくヨーロッパにも侵入したようですが、海外ではどのように対応しているのでしょうか。 | 日本以外にもドイツ、イタリアに侵入しました。ドイツでは強い処置をして根絶したと思われましたが、最近ごく少数の新たな被害が報告されています。イタリアでは、被害が確認されてからしばらく手をこまねいていたら、現在では特に中部で被害が大きくなっています。 |
| 10 | リアルタイムオンラインマッピングについて、詳しく教えて欲しいです。 | スマホあるいはPCから、ここで成虫を見た、ここで被害を見た、ここでは何もなかった、などをアンケート形式で提出できるシステムです。提出は誰でもできます。閲覧は、地域でまとめたメッシュデータならだれでも可能ですが、ピンポイントの情報は風評被害を防ぐために行政または登録された関係者に限られます。活用のされ方は地域ごとに異なっています。 |
| 11 | クビアカツヤカミキリの被害木は老木が多いのでしょうか、若い木が多いのでしょうか。樹齢と被害の傾向はありますか。 | 若く樹皮がすべすべした木は、老齢で大きく樹皮がごつごつした木よりも被害に遭いにくい傾向があります。ある地域で最初に被害にあうのはたいてい神社の御神木のような大きな木です。しかし、そこから若い木に広がっていくこともあり、若い木だから安全ということはありません。 |
| 12 | 原産地を含め、クビアカツヤカミキリの天敵のような生物は特定されているのでしょうか。 | 原産地では、天敵について野外での調査はあまり行われていません。日本国内では、アリの一部が幼虫や卵を攻撃して殺してしまうことは実験的に確認されています。その他、キツツキなど、天敵として機能する候補が見つかりつつあります。 |
| 13 | 樹幹注入の時期が5月と9月になっていますが、梅雨の時期でも良いですか。幼虫に対しての薬だと思うのですが、成虫にも効きますか。 | 木の中で食べている幼虫を駆除するもので、梅雨の時期でも効果はあります。成虫には効果がありません。 |
| 14 | ウメだとどうなるでしょうか。ウメはモモと同じでしょうか。他の果樹はどうですか。 | 私(浦野)はまだ調べていません。日本で被害が知られているのはウメ、スモモ、アンズなど、すべてバラ科の果樹です。リンゴやナシもバラ科ですが、今のところ被害の報告はありません。 |
| 15 | クビアカツヤカミキリの成長に気候面は関係するのでしょうか。寒さと生息の関係はありますか。 | 海外では、北はシベリアから南はベトナム周辺まで広がり、気候に対して適応度が高い特徴があります。日本では一世代に2年間要するが、寒い地域では3年間、暖かい地域では1年で成虫になります。このように、暑さ寒さと成長のサイクルの長さに関係があります。 |
| 16 | モモというと岡山県が浮かびますが、岡山県に被害はないのでしょうか。 | 岡山県ではまだ確認されていません。 |
| 17 | 丸太にしたことによる幼虫のサイズで、生存率への影響はないのでしょうか。野外で観察されるサイズと差はないのでしょうか。 | 幼虫が成長しきった時期に伐倒したので、サイズへの影響は少ないと思います。丸太にした時にたまたま一緒に切断したり、丸太の断面からの雨水の流入や逆に乾燥により死ぬなどして生存率への影響はあると思います。 |
| 18 | モモの方が幼虫が高密度で生育しているのに個体サイズに差が無い理由は何が考えられますか。 | 仮説の段階ですが、モモの方が肥料をやっているので窒素が多く生育が良くなったのではないかと考えています。今後、窒素の量も計測していきたいと思います。 |
| 19 | 今回検討したモモの場所に「たまたま」サクラより多くの成虫個体がいたという可能性はないのでしょうか。 | 今回の報告では確かにサクラとモモと1か所ずつしか調べていません。モモの方がサクラよりも被害が大きいという報告が被害が出ている県から以前よりあったので、それを定量的に確かめるために今回の調査を行いました。 |
| 20 | サクラ・モモの樹幹・材の窒素濃度を測定されましたか。簡単に分析可能なのでしょうか。 | 測定することはできますが、今回の研究ではまだ行っていません。過去の事例では、施肥により害虫の発育が良くなったり個体数が増えた例が報告されています。 |
| 21 | 薪割り機で2分割した断面の蛹室数の確認方法はどのように数えるのでしょうか。 | 2分割し出てきた蛹室に印をつけて数を数え、さらに2分割して新たに出てきた蛹室に印をつけて数を数え、それを繰り返して最終的にすべての蛹室の数を数えました。 |
| 22 | モモは直径の小さい木にもつくのに、サクラは太い木を選んでいるのはなぜでしょうか。 | 被害を受けているモモはほとんどが果樹園で、これらは比較的小さな木です。一方サクラの場合は被害木の大半が直径の大きな木で、小さい(若い)木はあまり産卵されないことが知られています。 |
| 23 | 材積あたり、とのことですが、サクラの方が材積における辺材部の割合が少ないと思われます。本種は主に辺材部の加害が知られており、この違いは差に影響するのではないでしょうか。 | 直径の大きなサクラ丸太ではご指摘の通り穿入しない部位の割合が高くなると考えられます。今回これらを計算から除くことをしませんでしたが、厳密に計算すればモモとサクラの差は10倍より小さくなると予想されます。 |
| 24 | 関東は埼玉県北部~群馬県南東部に多く、サンプルが局所的なため、分布密度が異なるのではないでしょうか。 | 成虫の局所的な生息密度に関しては、やはり被害木の密集するモモ園の方が高くなると思われます。 |
| 25 | サイズはなぜ前翅長なのですか。 | 体長はその時の状況(乾燥具合など)により変化する可能性があるため、変化しない前翅長を測りました。 |
| 26 | サクラよりモモの方が被害が多い理由として施肥の効果を挙げられていましたが、摂食量は同じでしょうか。成分分析はされたのでしょうか。 | 樹幹内の摂食量は調べていません。施肥の効果については、過去の研究例から考察可能な仮説として挙げたものです。成分分析は今後の課題としたいと思います。 |
| 27 | 府内16市町村名は公表できますか。 | 大阪府庁のHPで公開しています。 https://www.pref.osaka.lg.jp/midori/seibututayousei/kubiaka.html |
| 28 | 山林・森林地域への侵入は確認されているのでしょうか。 | 里山のソメイヨシノには被害が認められる場合があります。山林に自生するヤマザクラなどには被害は確認されていません。 |
| 29 | 枯れた木に樹幹注入して効果はあるのでしょうか。また、枯れた木にも幼虫は残っているのでしょうか。枯れた木にも産卵するのでしょうか。 | 枯れた木では薬剤が樹体内に巡らないので効果がないと思われます。枯れた時点で木の中にいた幼虫が成虫となる例を確認しています。しかし、枯れた木に成虫は来ないので産卵することはないと思います。 |
| 30 | 樹幹散布は降雨により効果は無くなるのでしょうか。 | 降雨量にもよりますが、薬剤が雨により流されることで薬効の低下が早まると考えられます。特に散布直後(薬液が乾燥するまで)に降雨にあうと薬効の低下が顕著ですので、晴天時に散布処理を行ってください。 |
| 31 | 樹幹注入で駆除した場合、樹勢の回復は見込めますか。 | 樹木内の幼虫を完全に駆除できた場合、時間はかかると思いますが、樹勢が回復する可能性はあると思います。 |
| 32 | 樹幹注入や薬剤散布等の化学的防除を行うことで、樹木や他の動植物に影響(弊害)を与える事例がありましたら教えてください。 | 薬剤は花や葉などに到達するので、花に来る昆虫などがいる場合にはその時期の薬剤注入は避けた方が良いと思います。サクラの場合にも、花が落ちてから(展葉してから)注入する必要があります。 |
| 33 | 産卵数に対して成虫を捕獲するのは、かなり効率が悪い気がしますが、どのくらい効果があるのでしょうか。 | 私たちが捕獲できる成虫は全体のほんの一部なので、成虫の捕獲は僅かな防除効果しか有しないと考えられますので、その他の防除方法を組み合わせることが必要です。 |
| 34 | 防除方法の中で、国などからの補助金の制度を活用できるものはあるでしょうか。 | 個人に対しての補助金制度は現在のところありません。自治体もしくは自治体が参加して協議会をつくり、協議会から駆除を含めた防除の経費を申請する事業が環境省にはあります(https://www.env.go.jp/press/110475.html)。 |
| 35 | クビアカツヤカミキリは何を頼りにバラ科樹木を探すのでしょうか。嗅覚が発達しているのですか。 | まだわかっていません。おそらく、寄主となる樹種に共通する揮発性物質を頼りに探してしているのではないかと推察されます。今後の研究により明らかにされると思います。 |
| 36 | 伐根できない場合は地際処理と言われていましたが、これは物理的に封じるということでしょうか。成虫が土から出てくることはないのでしょうか。 | 地際で伐る事により切株に残る幼虫の数を減らすことができるので、地際での伐採処理をお願いしています。また、根株にビニールシートを被覆することで、仮に成虫が出てきても拡散を防ぐことができます。土に埋もれた根から出てきた成虫が辛うじて脱出することがあるかもしれません。 |
| 37 | 大阪では被害が拡大を続けています。被害発見ができていないのではないでしょうか。被害の早期発見ができない理由はなんでしょうか。 | 被害の早期発見には、被害を発見するための調査を実施することが重要です。大阪府ではサクラが至るところに点在しているので、サクラ等を管理する者だけでなく多くの府民の協力を得ながら、できるだけ多くのサクラの被害調査を行うことが被害の早期発見に有効であると考えています。 |
| 38 | なぜ、サクラやモモに集中して寄生するのでしょうか。楓やポプラなど街路樹に寄生しないのはなぜですか。 バラ科以外を加害しない理由は何でしょうか。 |
カミキリムシには広食性(いろいろな樹種を利用するもの)と狭食性(樹種が限られているもの)がいて、狭食性のものは、視覚や嗅覚で寄生できる木を探しますが利用できる種以外はそのセンサーに引っかかってこないために産卵をしようとしません。本種はサクラ亜科の木を長い進化の歴史の中で利用してきていて、食べて栄養にするのも樹液から逃げるのも得意になっているため、その他の木を利用する必要がないから、寄主範囲が拡がっていかないことが推察されます。 |
| 39 | カキやポプラといったバラ科樹木以外にも被害が起きると聞きましたが、事実でしょうか。 | 海外の文献にはそのように書いてあったのですが、日本では被害地にあるカキもポプラも加害されていないので、私(山本)は事実ではないと考えています。 |
| 40 | サクラの種類に好き嫌いはありますか。 | ソメイヨシノの被害が多いのですが、ヤマザクラでも平地で植えられているものが加害されたことがあります。樹種よりも立地条件によって被害が激しくなるのかどうかが違ってくる印象があります。 |
| 41 | 昔からゴマダラカミキリによる果樹の大きな被害があったかと思いますが、今般のクビアカツヤカミキリが特に悪質である点はどんなことでしょうか。 | ゴマダラカミキリの産卵数とは桁が違う個数の卵を産むために被害があっという間に進展するところが恐ろしいところです。 |
| 42 | 樹皮の状態によって被害の受けやすさが異なるとのことでしたが、コケ等の影響はあるのでしょうか。 | コケが生えていることによって産卵しやすくなる可能性はあると思いますが、実際に確認はしていません。 |
| 43 | TVで六甲アイランド内でツヤハダゴマダラカミキリの被害が出ていることを知りました。これも特定外来生物でしょうか。 | 現在指定されていませんが、今後指定の可能性は高いと考えられます。 |
| 44 | パレットをウメなど細径の樹木で作ることはあまり考えられないと思うのですが、パレットからの発生事例はあるのでしょうか。 | 梱包材は物流急増時には、とにかく入手できた木から作っていたと聞きました。ウメ・モモはあまり大径になりませんが、利用されていたことがあったと考えています。パレットからの日本での発生の観察はありませんが、ドイツでは被害地そばの木箱で脱出痕が見つかっています。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.
