ここから本文です。
森林総合研究所関西支所令和5年度公開講演会の開催報告
開催報告
2023年7月12日(水曜日)13時30分より、龍谷大学響都ホール校友会館にて「森林総合研究所関西支所令和5年度公開講演会」を開催しました。
関西支所主催の公開講演会は、地域の皆様に森林の不思議さや奥深さ、現代社会との関わりについてわかりやすくお伝えすることを目的として、毎年開催しているものです。
当日は約240名の方々にご来場いただき、活気あふれる講演会となりました。
今回のテーマは「広葉樹のすすめー広葉樹林を『お宝』として活かすためにー」です。まず初めに、基調講演「地域活性につなげる広葉樹林の育成管理に向けて」を新潟大学の梶本卓也教授に行っていただきました。引き続きいて「広葉樹林を『お宝』とするために」「広葉樹林をどうやって伐る?ー伐採方法と生産コストー」「広葉樹林で使える木材はどれくらい?ー原木利用率の推定方法ー」「広葉樹林のお値段は?ー木材資源の価値ー」の4題の講演を森林総合研究所の研究者が行いました。
これらの講演により、これまであまり認められて来なかった広葉樹林の価値、その経済的な価値を引き出す伐採方法やそのコスト、複雑な樹形の広葉樹から得られる木材を伐る前に見積もる技術、それらをまとめて広葉樹林全体を評価する手法、などが紹介されました。
講演の後には、会場入口ロビーにて、関連研究プロジェクトの成果などを紹介するポスター発表を行いました。各ポスターについて担当研究者が内容を説明し、たくさんの方が熱心に耳を傾けておられました。
講演会の最後に登壇者5名によるパネルディスカッションを行い、広葉樹林やそこから得られる木材について様々な議論が交わされ、盛会のうちに終了しました。
来場者受付時には質問用紙を配布し、皆様から多くのご質問をいただきました。回答については本ページ末尾に掲載します。質問の内容は多岐にわたっており、この話題に対する皆様の関心の高さを改めて認識しました。
また、共に配布したアンケートにも、多くの回答をいただきました。これらは次年度以降の講演会の充実のために活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。


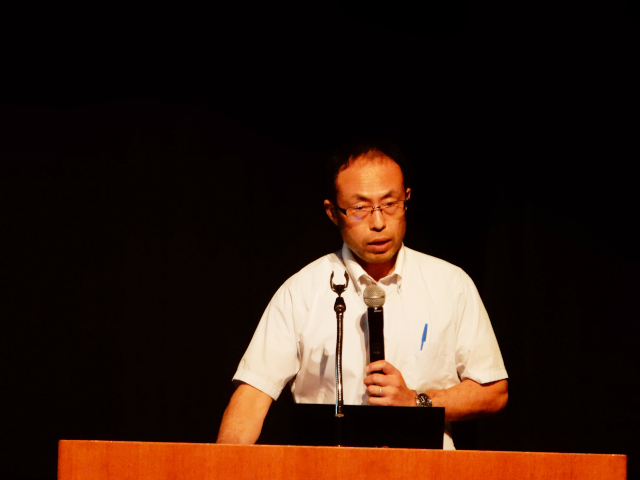



動画公開
講演の動画はYouTube「森林総研チャンネル」で公開しています。ぜひご視聴ください。
(講演名をクリックすると動画ページに移動します。)
基調講演 地域活性につなげる広葉樹林の育成管理に向けて
(新潟大学佐渡自然共生科学センター森林領域 教授 梶本 卓也 氏)
講演1. 広葉樹林を「お宝」とするために
(森林総合研究所 企画部研究評価科長 齊藤 哲)
講演2. 広葉樹林をどうやって伐る?―伐採方法と生産コスト―
(森林総合研究所 林業工学研究領域森林路網研究室長 鈴木 秀典)
講演3. 広葉樹林で使える木材はどれくらい?―原木利用率の推定方法―
(森林総合研究所 森林管理研究領域資源解析研究室長 小谷 英司)
講演4. 広葉樹林のお値段は?―木材資源の価値―
(森林総合研究所関西支所 森林生態研究グループ長 山下 直子)
森林総研関西支所の講演会に寄せられた質問と回答(Q&A)
ご来場者の皆様からいただいた、講演に関する質問に対する回答を掲載します。
なお、質問については、同種の質問をまとめるなど、編集を行っているものがございます。また、回答することが困難と判断したものについては、本ページへの掲載を割愛させていただきました。下記以外の質問がございましたら、地域連携推進室までお問合せください。
| Q1 | スノービーチプロジェクトではネットワーク作りに取り組んでいる方がいるとのことですが、こうした人材はどのように育成したら良いでしょうか。 広葉樹林整備の方法から持続的な木材活用まで、複合的な知識を持つコーディネーターを行政が育てるにはどのような方法が考えられますか。 |
| A1 | ネットワークの核になる方(コーディネータ役)は、自身の専門に関する豊富な経験を積んだ上で、他分野や業種の人と直接向き合って話を進めることができる人が適していると考えます。したがって、そうした方の養成は簡単ではないと思いますが、川上・川下側を問わず、そうしたことに関心ある若い人を将来に向けて育てるという考えにたって、ネットワーク作りの方法などの養成講座や情報交換の場をつくる取り組みを、県など行政機関がサポートするのがいいと考えられます。 |
|
Q2 |
広葉樹林全体のどれだけを伐採し、そのサイクルを考える全体のコーディネートは誰がイニシアティブをとるのでしょうか。 |
|
A2 |
それぞれの森林や関係するメンバー構成によって状況が異なるため、画一的に言うことはできませんが、スノービーチプロジェクトが関わっている大白川生産森林組合の場合ですと、プロジェクトのコーディネータ役と森林組合が間伐されたブナ林の生育状況を観察しながら、順次森林経営計画を樹立し、数年先までの利用間伐による出材状況を川中や川下の関係者に適宜伝えるようにしています。 |
|
Q3 |
木材には地域性(郷土的習慣)がありますが、それをどのように生かしたチームを作ることができるでしょうか。 |
|
A3 |
日本の広葉樹林は、およそ7つの地域に優占樹種や気候条件等の特徴で分けることができます。地域特性を正しく理解した上で、例えば1種が優占する林であれば、その樹種の多様な利用方法に着目する、複数の樹種が混交している林であれば、違った樹種を用いて同じ製品を目指す、などの色々な方針を考えることが大切ではないかと考えます。 |
|
Q4 |
スノービーチプロジェクトの中で虫害材の製品が紹介されていましたが、需要はどの程度ありますか。 |
|
A4 |
ダメージ材を使うことの意義と自然のデザインの面白さを理解した家具製造店、建築デザイナー、クラフト作家が使っています。その多くは偽心材で、板材の6~7割程度を占めます。穴あき材は1~2割程度で、透明レジンで埋めてから加工している場合が少なくありません。 |
| Q5 | ブナは売れるようですが、シイ、カシ林はどうでしょうか。 |
| A5 | シイ、カシ類は、材質的に船舶や車両、枕木など特殊用材が中心で、家具やフローリング、木工品など一般的な用材にあまり向いていないこともあり、それらの用材生産に取り組む業者は少ないようです。ただし、戦前までは農具など生活用品全般に広く使われていたので、今後は新しい用途を見つけ出す必要がありそうです。 |
| Q6 | 人材育成に関してあまり悲観していないと話していましたが、新しく木に関わる仕事を選ぶ人たちが今後増えていくと思いますか。それはどういうところで実感しますか。 |
| A6 | 実際の山の現場で働く若い方の育成に関しては、全国的にも林業の専門学校がほぼ各県にでき、着実に学ぶ若い人も増えつつある状況です。ただし、こうした専門学校での指導や教育は、今問題になってる針葉樹人工林の主伐や再造林を進めるための技術獲得のための実習が中心になっています。今後は広葉樹林の問題についてもカリキュラムに加え、森林や樹木の生態に関する知識など幅広い情報も学べるような工夫が必要と考えています。 |
| Q7 | 大まかにhaあたり何本程度で成立してるのでしょうか。 |
| A7 | 広葉樹人工林での成立本数は、管理状況によって異なります。天然林(二次林含む)の場合は、様々な大きさや樹種で構成されており、最小サイズをいくつに設定して数えるか、用材として使える樹種だけ対象として数えるかなどで成立する本数は大きく変わります。成熟した常緑広葉樹林の場合で、胸高直径5cm以上の高木種の本数が1,000~2,000本/haという例がありますが、これも森林タイプや環境条件によって異なるため、一般的に「何本程度で成立している」ということはできません。 |
| Q8 | 建築用材として活用できるよう考えるべきではないでしょうか。外材のタモの価格が上がってゴムノキの集成カウンターが販売されたように、国産広葉樹の集成材などは考えられませんか。 |
| A8 | 広葉樹は、建築用材として使える部分が少なく安定的に供給できないため、安易に全てをチップとして安価に取引されるケースが多々あります。ご指摘のとおり、建築用材として活用できるようであればそのようにするべきと考えます。安定的に供給できない中で建築用材として可能な広葉樹がでたときに価値ある建築用材として市場に出せる仕組みが十分にできていないのが現状で(そのため全て安価に売られる)、そこをいかに改善していくかが重要と考えます。また、建築用材として使えない部分も多く、建築用材以外でも広葉樹独自の価値ある使い道を開拓していくことも重要と考えます。集成材として使う方法もありますが、広葉樹は種によって多様な特徴をもち、その特徴を活かしたより価値のある使い方を開拓できる可能性も大きいと考えます。 |
| Q9 | ユーカリ等早生の外来種を植える計画が佐用町でありますが、生産性の良し悪しの分や生態系への影響や、昨今の災害時の植生の対応の可否についてどう思いますか。 広葉樹の伐採の後、どのような樹種を植え、増やしていけば、今後につながると思いますか。 |
| A9 | 外来種の導入については、生態系への影響を優先させるか、厳密な管理下で生態系への影響を最小限にしつつ木材生産を優先させるか、あるいは防災リスクの観点を最優先させるかなど、森林に期待する役割によって考えが異なります。ユーカリについては過去に九州で導入した事例もあり、過去の事例を調べてみることも参考になると思います。在来種(元々そこにあった樹種)で再生させるのが理想的ですが、状況に応じた柔軟な判断が必要だと考えます。一つの基準(木材生産、自然保護、防災)だけでなく、目指す役割に応じて総合的に考えることが必要です。 |
|
Q10 |
今回の講演のキーワードとして「単木管理」があるように感じました。 スギ・ヒノキなどの一斉人工林における全体管理に対し、単木管理は管理コストが高くなるように思いますが、実際はどうなのでしょうか。 また、単木管理の管理手法としてはどのようなものがありますか。 |
|
A10 |
ご指摘のとおり、「単木管理」は今後の管理指針として重要な視点の一つと考えます。講演会の中で一部触れたように、山に生えている状態のまま個々の木の大きさ・状態などの情報を、例えば、地上レーザーや端末による動画・写真撮影等を使って把握しておき、ニーズにあった大きさ・状態の木だけを切り出す、ということも管理手法の一つといえます。ただ、管理コストが高くなるのも指摘のとおりで、それに見合った用途の開拓・価格形成が必要です。そのシステムをどのように作っていくかが難しいところです。 |
| Q11 | 広葉樹の造材作業には、グラップルソーとチェーンソーの併用が良いとのことですが、集材作業には、どのような機械が効率が良いと考えますか。現場ではどのような機械が使われていることが多いのでしょうか。 |
| A11 | 今回の調査結果では、最も労働生産性(1人1時間あたりの生産量)が高くなったのはフォワーダ等を用いた車両系集材システムでした。しかし、地形条件などに応じてタワーヤーダや集材機などが選択されることもあり、それぞれの現場で活用可能な機械が使われています。 |
| Q12 | グラップル活用して、太い部分のみ生産、細い部分は山に残すという趣旨の説明がありましたが、山に残す細い材はチップを想定されているのでしょうか。 |
| A12 | 地域のニーズに応じて、チップや薪にすることが想定されます。 |
| Q13 | グラップルソーは路網を整備しないと使えないのでしょうか。 |
| A13 | 必ずしも多くの路網を整備する必要はありません。比較的少ない路網で使用できるタワーヤーダや集材機などで集材した後、土場でグラップルソーを使用することもあります。 |
| Q14 | 大径木の伐採は特別な技術が必要ではないのでしょうか。30cm~50cmぐらいまでを想定しているのでしょうか。 |
|
A14 |
大径木の伐採には技術や経験を要します。また、通常の大きさの木と比較して、伐採や集材作業に要する時間が特に大きくなるため、今回の調査では直径が50cmを大きく超える大径木は対象外としています。 |
| Q15 | グラップルソーでの広葉樹の枝払い等の細かい作業に時間がかかるとのことですが、海外のグラップルソーは揺動式で効率よく作業ができるように思います。固定式と揺動式の差はどのくらいありますか。 |
| A15 | 固定式、揺動式それぞれに効率の良い(得意とする)動作があり、必ずしもどちらかの効率が良いとは言えません。また、日本で使用されるグラップルソーはほとんどすべて固定式であるため、揺動式のグラップルソーで作業したときのデータがありません。 |
| Q16 | 造材が1番コストがかかるとのことですが、チップ目的の伐採の場合のコストはどのくらい下がるのでしょうか。 |
| A16 | 講演2で紹介した事例では造材作業の生産性が最も低くなっていましたが、この作業はチップ生産を目的とするものでした。チップにする場所までフォワーダによる集材を行ったのですが、その効率を重視して丸太の長さをある程度そろえる必要があったことから、チップ目的でも造材作業が行われました。そのため、チップ目的の作業であっても、必ずしもコストが下がるとは言えません。 |
| Q17 | 生産コスト、林分あたりの収益について、皆伐することを前提とされているのでしょうか。広葉樹林の持続性、公益的機能を考えると皆伐は単純な望ましい方法ではないと考えます。その上で択伐する場合のコスト、収益についてはどのようになるか教えてください。 |
| A17 | 今回行った試算では皆伐を前提としました。そのため、択伐は調査対象としておらず、コスト、収益について回答できるデータはありません。 |
| Q18 | 岩手県と山形県で原木利用率の差が大きいのはなぜでしょうか。 |
| A18 | 積雪量の違いです。山形県の調査地は、国内でも有数の多雪地帯で最大積雪深が4mあります。この雪で根曲がりし、幹の上部も曲がり、真直ぐな幹が短いようです。 |
| Q19 | 推定方法が2.2mでは建築では短いと思いますが、どのように多用することを考えていますか。 |
| A19 | スギ・ヒノキのような針葉樹は、4mや3.6mで柱などが主となります。一方で、広葉樹の取り扱いが国内有数の岩手県木材流通センターでの聞き取りによると、主にはフローリング等の板材ですが、コナラなど多種の広葉樹を扱っており、樹種によって様々に用途が異なります。 |
| Q20 | 広葉樹材の(板材)乾燥コストや歩止まりは樹種によってどのくらいなのでしょうか。以前、クヌギでは歩止まりは数パーセントだったように思います。 |
| A20 | 木材市場までの聞き取りはしましたが、本件は製材所の聞き取りが必要であり、今回はそこまで調査しておりません。 |
| Q21 | 細り表を見せてほしいです。 |
| A21 | 本研究において参照した細り表は以下の2件です。広葉樹の細り表はほとんどありません。 岐阜県森林科学研究所(2004)木材生産のための落葉広葉樹二次林の除伐・間伐のしかた,20pp 横井 秀一(2004) 樹高を必要としない落葉広葉樹の細り表の調製,森林計画学会誌38巻1号 p.23-28 |
| Q22 | 広葉樹の平均蓄積がまだまだ少ないのは樹齢が若いせいでしょうか。 |
| A22 | 広葉樹の蓄積は、場所によって大きく違いがあります。広葉樹の平均蓄積が少ない理由として、林齢が若いことや、他の針葉樹等が優占している、立地条件が悪いなどが考えられます。 |
| Q23 | 薪ならチップよりは高く売れ、現状では現実的だと思うのですが、薪の可能性についてどう考えますか。 |
| A23 | 薪は、ピザ窯やパン窯用等としての利用や、近年は、備蓄用や緊急災害対応用の燃料としても需要があり、薪ストーブの販売台数の増加等を背景に、生産量は増加傾向にあります。価格は、長期的に上昇傾向で推移しておりますので、今後も有用な使い道の一つと考えられます。 |
| Q24 | 混交林化という考えがありますが、地域活性や持続性の面から広葉樹を植栽することについて、どのように考えますか。 |
| A24 | 天然更新が困難な場合は、植栽によって森林の再生を図る必要があると考えます。ただし、その際に使う苗木は、地域固有の遺伝的多様性を保全するために、地元の山の母樹から種子を採取して育成した地域性の高い苗木を使うことが望ましく、そのような苗木の生産・供給体制の構築が重要と考えます。 |
| Q25 | 広葉樹の原木使用の価格について、例えば3万円/m³以上になる丸太の特徴は、針葉樹の特徴と同じでしょうか(完満、曲がりが少ない、腐食・水割ない、年輪幅が一定等)。 |
| A25 | 針葉樹の特徴以外に、流行の樹種であるかどうかや、芯の位置、年輪幅が密、色合い、杢の有無などが価格に影響しています。 |
| Q26 | 広葉樹のサクラのデータがありませんでしたが、市場の要望はあるのではないのでしょうか。 |
| A26 | 発表には含めませんでしたが、サクラは原木市場での取引量の多い樹種の1つです。 |
| Q27 | 30~50cm程度を建築材としての製品化について、もっと企業等と連携することを考える必要があるのではないでしょうか。 |
| A27 | 建築材としての製品化については、企業等と連携し強度や材質等の規格化に向けて取り組んでいくことが重要と考えます。 |
| Q28 | 丸太の状態で樹種を判定するコツはありますか。簡易に判定できる方法、または困難でも確実な方法はありますか。 |
| A28 | 樹木の同定は、特徴的な樹種であれば丸太でもわかるかもしれませんが、樹皮や材質だけでは難しい場合が多いです。葉や実、枝ぶり、生育場所などの情報が得られる立木の段階で、樹種を判別することがベストです。 |
| Q29 | 広葉樹を取り扱う原木市場を教えてほしいです。 また、市場の広葉樹用材の基本の長さ・樹種及び対象となる太さを教えてください。 |
| A29 | 全国各地に原木市場があり、有名なところでは、旭川地方木材協会、岐阜県銘木協同組合、岩手県森林組合連合会の木材流通センターなどがあります。取り扱っている樹種や材の長さは各市場で様々ですが、2m程度の材が多く、平均的な太さは30cm程度ですが、近年はもっと小径の材も出展されています。 |
| Q30 | お宝の木をムダにしないためには、どこで、どんな大きさのどんな木を伐採するかがわかるネットワークを作り、木材を使用する業者とタイアップする必要があると思いますが、いかかでしょうか。 |
| A30 | 各地域で、川上と川中を繋げるコーディネーター的役割の人材が必要と考えます。地元の森林資源の現状を把握し、どこで売れるかという販路の情報と繋げるだけではなく、伐採後の森林再生をどのように図り資源の持続性を担保するかという点まで俯瞰できることが、地域に根差したコーディネータとして不可欠な技量と考えます。 |
| Q31 | 関西地域ではナラ枯れが激しかったと思いますが、大径木の利用にどのくらいの影響があったのでしょうか。 また、利用できる材積は回復しているのでしょうか。 |
| A31 | 関西地域のみならず、ナラ枯れ枯損量は2010年をピークにいったん減少した後、近年また増えつつあります。大径木ほど大きな影響があったと思われますが、具体的な数字はお示しできません。被害が収まった地域で材積が回復しているかどうかは、その地域ごとに状況が異なると考えられます。 |
謝辞
回答を作成するにあたり、講演会の登壇者と共に、新潟大学名誉教授の紙谷智彦氏にも特別にご協力いただきました。ここに記して感謝申し上げます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.
