ここから本文です。
森林総合研究所関西支所令和6年度公開講演会の開催報告
開催報告
2024年7月10日(水曜日)13時30分より、京都市呉竹文化センターホールにて「森林総合研究所関西支所令和6年度公開講演会」を開催しました。
関西支所主催の公開講演会は、地域の皆様に森林の不思議さや奥深さ、現代社会との関わりについてわかりやすくお伝えすることを目的として、毎年開催しているものです。
当日は約108名の方々にご来場いただき、活気あふれる講演会となりました。
今回のテーマは「快適な春につなげる森林(もり)づくりー花粉症対策技術開発の現在(いま)ー」でした。まず初めに、基調講演「空飛ぶ花粉と花粉症の予防治療ー空中花粉から見えてきた諸課題ー」を富山医療生活協同組合富山協立病院の寺西秀豊医師に行っていただきました。引き続きいて「花粉の量を知るー雄花の着き具合からの予測ー」「花粉の少ないスギを創るー花粉症対策品種の開発ー」「飛び交う花粉を減らすー新しい花粉飛散防止剤の開発ー」の3題の講演を森林総合研究所の研究者が行いました。
これらの講演により、スギ花粉症の原因や対策を概観するとともに、森林総合研究所が取り組んでいる花粉の飛散量を予測し抑制する最新の研究成果を紹介しました。
講演後は会場入口ロビーにて、関連研究プロジェクトの成果などを紹介するポスターの展示および発表を行いました。
講演会の最後には、登壇者4名によるパネルディスカッションを行い、「花粉を減らすために情報と技術をどのように駆使していけばよいか?」をテーマに議論が交わされ、盛会のうちに終了しました。
来場者受には質問用紙を配布し、皆様から多くのご質問をいただきました。回答については本ページ末尾に掲載します。質問の内容は多岐にわたっており、この話題に対する皆様の関心の高さを改めて認識しました。
また、共に配布したアンケートにも、多くの回答をいただきました。これらは次年度以降の講演会の充実のために活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。
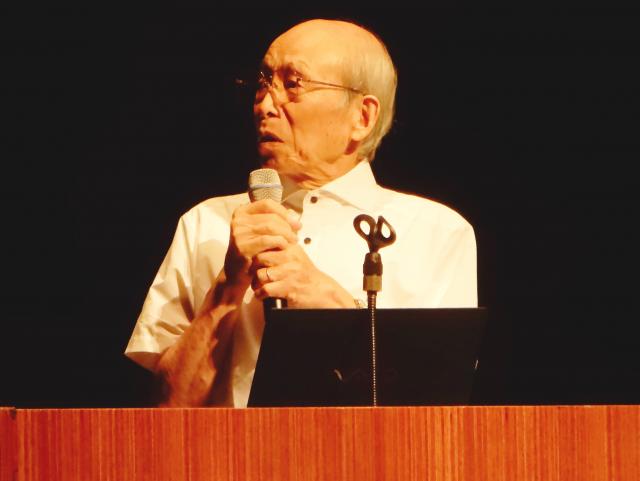
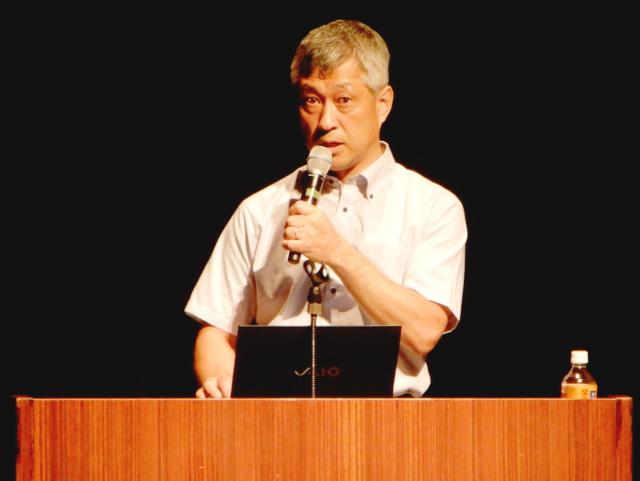




動画公開
講演の動画はYouTube「森林総研チャンネル」で公開しています。ぜひご視聴ください。
(講演名をクリックすると動画ページに移動します。)
基調講演 空飛ぶ花粉と花粉症の予防治療ー空中花粉から見えてきた諸課題ー
(富山医療生活協同組合富山協立病院 医師 元富山大学医学部准教授 寺西 秀豊 氏)
講演1. 花粉の量を知るー雄花の着き具合からの予測ー
(森林総合研究所 森林植生研究領域チーム長(花粉動態研究担当) 倉本 惠生)
講演2. 花粉の少ないスギを創るー花粉症対策品種の開発ー
(森林総合研究所林木育種センター関西育種場 育種課長 山野邉 太郎)
講演3. 飛び交う花粉を減らすー新しい花粉飛散防止剤の開発ー
(森林総合研究所関西支所 生物被害研究グループ長 市原 優)
森林総研関西支所の講演会に寄せられた質問と回答(Q&A)
ご来場者の皆様からいただいた、講演に関する質問に対する回答を掲載します。
なお、質問については、同種の質問をまとめるなど、編集を行っているものがございます。また、回答することが困難と判断したものについては、本ページへの掲載を割愛させていただきました。下記以外の質問がございましたら、地域連携推進室までお問合せください。
| 1 |
Q.ダーラム器以外の花粉の検知方法はありますか。 A.花粉を検索する方法は他にもあります。今回は詳しく説明しませんでしたが、バーカード法というのが世界的には一般的です。多少手間がかかりますが、空気体積当たりにどれだけ花粉が含まれるかを定量的に測定できます。最近は、花粉を自動的にモニターできる機器も試作されています。数年前まで環境省が「はなこさん」という全国的な花粉観測システムを試みていました。現在のところ、こうした花粉観測システムの評価は十分には定まっていません。 |
|
2 |
Q.花粉アレルギーを持っているのは人間だけなのでしょうか。 A.花粉アレルギーは人間だけに発症するわけではありません。ニホンザルでも花粉アレルギーが起こっていると報告されています。また、ネズミなどの実験動物でもアレルギーを起こすとの報告もあります。 |
|
3 |
Q.花粉症はいろいろな条件が複雑に関係して発病するものと言われています。感作状態を減らすため、いろいろな条件を細かく分析して、発病との関係性を明らかにし、その上で影響の高いもの、因子から優先的に対応するべきと考えますがいかがでしょうか。 A.花粉症の発症にはいろんな条件があり、要因としては花粉暴露とともに、大気汚染、浮遊粒子、食事栄養の問題、体質遺伝の問題なども考えられています。都市と農村では、これら要因の関連性の程度が違っている可能性もあることから、様々な調査を積み重ねて、地域性を加味しながらの総合的な検討が大切だと思います。 |
|
4 |
Q.スギ花粉の形が変わると特徴も変わりますか、また、花粉症に影響ありますか。 A.スギ花粉は様々な状況で形が変わったり、破裂したりすることが知られています。それが花粉症にどのような影響があるか、まだ分かっていないと思います。ただ、花粉が粉砕され小さい花粉アレルゲンとして吸入されると、下気道と言われる、肺の奥の方に入りやすくなると考えられます。そうした場合、喘息様の症状が出やすくなる可能性もあるかと思います。 |
| 5 |
Q.「空飛ぶ花粉」とほぼ同時期に中国大陸からの黄砂の飛散が目立ちますが、医学的見地から、これらの事象の人体・健康への被害は、同等なのか、複合的なのか、全く別物なのか、いかがでしょうか。 A.スギ花粉が飛ぶ時期に大陸の方から黄砂が飛んでくることがあります。人によっては、そうした時期に、花粉症の症状悪化を自覚することもあるようです。しかし、黄砂の直接的影響なのか、黄砂とどのように関係しているのか等、確定的な証拠は無いと思います。 |
| 6 |
Q.基調講演の要旨図3で1995,2001,2011,2019年の4ポイントが特別高い値を示しているのはなぜですか。 A.ご指摘のとおり1995年など、スギ花粉の飛散量が特別多い年があります。これには、前年の7月、8月の温度、湿度が関係しています。前年の気温が高く、湿度が低いと花粉飛散量が多くなります。また前年の飛散量が多いと次の年の花粉量が少なくなる傾向があります。そうした要因の組み合わせで花粉量の特別多い年が形成されていると考えられます。 |
| 7 |
Q.花粉の予測において、誤差はどれほど生じることがあるのでしょうか。 A.毎春の花粉量の予測は、前年夏(雄花芽が作られ始める時期)の気象条件から行う方法と、作られた雄花芽を秋冬に目視した着花度から行う方法があります。毎春の雄花の量は、前夏の気象条件と前年(春)に着けた雄花の量に影響されます。このため、雄花の着き方から予測するやり方か、気象条件と前年の雄花量の両者から予測する方法が比較的誤差が少ないです。ただし、雄花の着き方から予測しても年によって実際の花粉量が予測の6~7割程度であったり、逆に予測の1.5~2倍になることがありました。前者は花粉の飛散時期に雨が多い場合や風が弱い場合に、後者はヒノキの着花が非常に多い年に見られました。 |
| 8 |
Q.スギ・ヒノキ花粉が優先度の高い花粉症対策の1つであるという前提での研究ですが、次の世代に引き続くべきNatural Friendlyな研究と言えるのでしょうか、この点について研究者として疑問をお持ちではないですか。 A.戦後大量に植林されたスギ・ヒノキからの花粉の発生が、花粉症の一因として指摘されていることから、その影響を減らして行くことは必要なことであると考えます。過伐により禿山となった林地に植林したことは地域や地球の自然の回復を目指したことでもあり、より良い生態系のバランスをこれからも探し続けて行くことが科学者として求められていることであると考えています。 |
| 9 |
Q.倉本さんの意見に同感します。川下の利用の問題、川上の林業者の育成(外国人労働者の雇用の問題も含め)、国の政策としてトータルで対応していかなければ、単純なスギ・ヒノキ花粉症対策で収まる課題ではないと思います。是非、総研も横ぐしで頑張っていただきたいと期待しています。 A.ご意見ありがとうございます。伐採・植え替えを進めるための対策技術も、(伐らずに止める)飛散防止技術も、どちらも条件にあわせて使い分けることが重要です。それは花粉が多いだけでなく同じ齢級に偏りすぎている現在のスギ・ヒノキ人工林の齢級を補正したり、条件によっては広葉樹林に転換するなど、森林の配置や機能を適正化する意味でも重要です。まさに横串で頑張ってまいりたいと思います。 |
|
10 |
Q.雄花の着き方によりスギ花粉飛散量を予測されていますが、発生源対策として、その年のつき方が将来とも発生源として重要と言い切れるのでしょうか(年による着き方のバラつきはないのですか)。 A.講演1では東京都のスギ林の昨年冬の雄花の着き方を例として示しましたが、雄花の着き方は同じスギ林でも年によって変わり、多い・少ないがあります。各春の各地域の花粉の多い少ないは秋冬の雄花の着き方から予測できます。一方で、どのスギ林で花粉が多いのか、あるいはどのような条件のスギ林で雄花が多いのか、すなわち花粉源としてより影響が大きいのかは、4,5年以上の着花調査の結果をもとに分析します。 |
| 11 |
Q.今年から全国で飛散調査を行うとのことですが、調査地は都市部から離れており、風向きや地形により花粉が多くても発症の頻度が異なると思われます。距離や地形等は考慮しなくてもよいのですか。 A.各都道府県のスギ林の分布を考慮して調査する林を選んでいます。この際に、県都などの都市部からの距離や標高が様々になるようにも選んでいます。スギ花粉は相当の高度まで風に乗って上がってから都市部まで運ばれますので、県レベルの距離であれば、風向きの影響はありますが、山があっても多少距離があっても山林から都市まで運ばれます。 |
| 12 |
Q.飛散防止の効果が期待できますが、全スギ林で実施するには非現実と思われます。どのくらいの面積に対してどのくらい花粉量を低下させるか、目標値などがあれば教えてください。 A.飛散防止剤も、伐採・植え替えによる削減も、花粉をこれだけ削減すればどれだけの発症を抑えられるかについては十分な知見がありません。森林での放出削減と都市部の空中花粉の減少、さらに発症者の減少や症状軽減との関係を検証する大規模な疫学調査が必要になります。一方、各県の花粉症の人の割合と、各県のスギ林あたりの雄花の推定量(雄花調査による着花指数から推定)には関係があることから、スギ林での花粉削減が有効であることは確かだと思います。また、飛散防止剤を全スギ林で実施することは資材やコストの面からも非現実的ですが、森林管理の面からも伐れない林や迂闊に伐らない方がよい林に対して優先的に施用すべきと考えております。 |
| 13 |
Q.目視によるスギ花粉量調査は、決まった方法で全国一律で行っていると思いますが、その方法の採用に森林総研は何か関わっているのでしょうか。 A.目視により各スギ林で40本ほどの個々の木の雄花の着き具合を4段階の度数で評価し、度数ごとに点数を与えて集計します。この集計点数がスギ林の実際の雄花数と関係することを森林総研が中心となって明らかにしました。また、評価基準や調査本数の設定にも森林総研が関わりました。こうした結果に基づいて、現場で実施しやすいシンプルな着花度の評価からスギ林の雄花数が推定でき、花粉量の予測に使えるようになっています。 |
| 14 |
Q.なぜ着花調査区域から紀伊半島や九州南部がはずれていたのですか。(偏西風?)また、なぜ今回から全県で行うことにしたのでしょうか。 A.約25年前に調査が開始されており、講演者は調査の一部を途中から引き継いだため、一部地域が外れた経緯は把握しておりません。当時、人口の集中する大都市圏とその近県から重点的に調査することとし、予算や人員の都合から大都市圏から遠い、あるいは地形的に山脈などで隔てられている地域の調査を行わなかった可能性があります。例えば、南九州は最も近い大都市圏の福岡・北九州圏から山地で隔てられており距離もあります。紀伊半島は京阪神地域に距離的には近いですが、山脈によって遮られていると考えられたからだと思います。今回、スギ人工林のある全都道府県に調査を拡大するのは、(1)国民病といわれるくらい患者数が多く首都圏などの人口密集域に限らずスギ林のある全都道府県で花粉情報を出すべきだと考えられているからです。各県で人口の多い都市域に近接するスギ林はまずは自県のスギ林であることが多いです。(2)一方で隣県のスギ林からも花粉は飛散しますので各県にとって隣県のスギ林の着花は重要な情報になります。 |
| 15 |
Q.京都の北山に無花粉スギ(白杉、台杉?)があると言われていますが、京都固有種(無花粉)として生産することは可能ですか。 A.講演2でご紹介したとおり、林木育種センターでは、優良品種・技術評価委員会を開催して、外部委員のご助言をいただきながら無花粉品種を開発する手続きを構築しております。この委員会は、都道府県単独での申請も受理し評価することが可能です。京都府内のスギでしたら、京都府の育種担当部署を通じて、林木育種センター関西育種場までご相談いただけましたら、具体的に申請をするために必要な調査事項をお伝えすることができます。 |
| 16 |
Q.花粉が少ない品種が広がることで生態(例えばスギ花粉を必要とする動物や菌類など)への影響はないのでしょうか。 A.どの林分に何を植えるのかは、土地所有者の判断になりますが、林野庁がスギ花粉発生源対策推進方針で定義している花粉の少ないスギは、あくまでもいずれ収穫される木材生産林に植栽するスギであって、保全すべき貴重な自然環境に植栽するスギではありません。森林経営は自然との共存に配慮して初めて成り立つので、土地所有者が、保全すべき貴重なスギ林分やその生態系へ悪影響を及ぼす場所に花粉の少ないスギを植栽することは想定しにくいです。 |
| 17 |
Q.花粉を産生しないがスギの精鋭樹としては優秀な苗木に、長い将来的に置き換わったとして、スギの自然交配による繁殖は途絶してしまうのでしょうか。 A.無花粉スギは花粉は飛散しませんが、雌花は健全です。また、無花粉遺伝子をヘテロで持つスギは受精能力のある花粉を飛散しますので、繁殖が途絶えることはありません。林木育種センターでは、この繁殖特性を生かし、さらなる交配で次世代化を進め、無花粉スギの改良を進めていきます。 |
| 18 |
Q.スギ以外の花粉に、飛散防止剤は効果がありますか。 A.今回開発した植物ホルモンを用いた花粉飛散防止剤の一部は、スギ以外にヒノキとシラカンバに効果が認められました。 |
| 19 |
Q.品種改良のようにシドウィア菌の適する環境を広げることはできないのでしょうか。 A.もしも、冬季に乾燥する地域で活発に雄花を枯らしている菌株があるとすれば、より乾燥に対する強いものを選抜できるかもしれませんが、現時点ではそのような菌株は得られていません。 |
| 20 |
Q.花粉防止剤が無事に上市され、空中散布できるようになった時、「農薬空散=人体・水環境への悪影響」という近隣住民からのクレームが心配されますが、実際の人体・水環境への影響の有無及び住民への説得方法等の考えがあれば知りたいです。 A.シドウィア菌は、自然界に元々存在するスギの雄花に特異的に寄生する菌であるため、他の植物や動物、人への影響は、一般的な化学農薬と比較すると極めて小さいと考えています。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.
