研究紹介 > 刊行物 > 研究成果選集 > 第2期 中期計画成果集 > 重点課題アアb 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発
更新日:2011年6月10日
ここから本文です。
重点課題アアb 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発
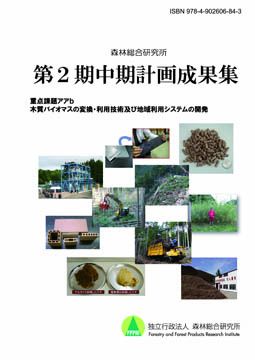
|
ファイルをダウンロード |
- 第2期中期計画成果集 重点課題アアb 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発
- 編集・発行:森林総合研究所
- 発行日:平成23年3月
- ISBN:978-4-902606-84-3
目次
- スギ林地残材からの木質バイオエタノール製造技術の開発
国内未利用バイオマス資源中、最大であるスギ林地残材からのバイオエタノール製造技術を開発しました。
- 木質バイオエタノール製造実証プラントでのエタノール生産
秋田県北秋田市に木材チップ1.5t /日の処理能力を持つプラントを建設し、アルカリ蒸解・酵素糖化法によるバイオエタノール製造実証試験を行いました。
- オイルパーム廃材をしぼってバイオエタノールを製造する
オイルパームの幹は熱帯産未利用バイオマスであり、その材をしぼって得られる液がバイオエタノール製造の有力な糖原料となりうることを明らかにしました。
- リグニンから鉛電池の充電性能改善剤を製造する
バイオマス成分であるリグニンを化学的に改質することで、鉛電池の充電性能を改善する負極添加剤を開発しました。
- リグニンの両親媒性化で木質バイオマス総合利用を推進
両親媒性リグニンはコンクリート混和剤や酵素安定化剤として高度利用可能でバイオマス総合利用に貢献します。
- バイオプロセスを用いたリグニンからのグリーンプラスチックの製造
木質バイオマスの構成成分であるリグニンから、組換え微生物バイオリアクターを用いてプラスチック原料となるPDC(2- ピロン-4,6- ジカルボン酸)を大量に生産し、それを原料にした高強度エポキシ接着剤、伸縮性ポリウレタンの製造に成功しました。
- 高性能な木材・プラスチック複合材(混練型WPC)の製造
未利用木材と廃プラスチックから高い耐候性や熱流動性を持つ複合材を開発しました。
- 経済的な林地残材のエネルギー利用とは
木質バイオマスは、チップボイラーによる熱利用の経済性が最も高く、燃料チップが10 円/ 生kg以下であればA 重油(70 円/L)と対抗できることがわかりました。
- 木質バイオマスの供給ポテンシャルが大きい地域はどこか?
木質バイオマスの発生量と供給コストからその経済的供給ポテンシャルを推計した結果、大規模プラントの設置に適した6 つの地域が明らかとなりました。
- 林業バイオマスを収集・運搬する機械の開発
造材作業と破砕作業の2工程処理が可能なチッパー機能付きプロセッサ、林地残材の減容化が可能なバイオマス対応型フォワーダを開発しました。
- 岐阜中山間地域における木質バイオマスの有効利用モデルの開発
高山市をモデルとして、木質バイオマスの供給、需要、利用技術を組み合わせたバイオマス利用モデルを構築し、樹皮を用いたガス化プラントの実証試験を通してモデルの評価を行います。
- バイオマス資源作物「ヤナギ」は初期生長が早く生産性が大きい
北海道下川町で育成したエゾノキヌヤナギは、年間8-12ton(乾燥重量)成長します。3 年毎の収穫、21年間で7 回の収穫作業を想定すると、生産コストは1万円/ton になります。
- 木材利用による二酸化炭素削減効果の定量的評価
木材を積極的に使うことによりどのぐらいの二酸化炭素削減効果が得られるかをシミュレーションしました。
- 中国・アセアン諸国における未利用バイオマス資源有効利用のための連携
アジアにおける持続可能な木質バイオマス利用技術を開発するため、各国の研究組織と連携して木質バイオマス利用の現状の調査を行いました。
- 木質ペレットのLCA(ライフサイクルアセスメント)と高性能化
木質ペレットの製造エネルギーを明らかにするとともに、熱処理を施すことで高性能な木質ペレットをつくることができました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.
