研究紹介 > 刊行物 > 研究成果選集 > 第2期 中期計画成果集 > 重点課題イイb 森林生態系における生物群集の動態の解明
更新日:2011年6月10日
ここから本文です。
重点課題イイb 森林生態系における生物群集の動態の解明
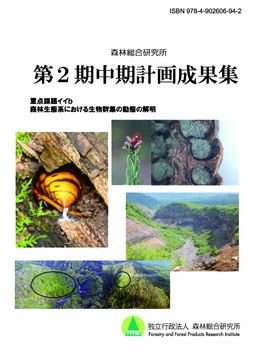
|
ファイルをダウンロード |
- 第2期中期計画成果集 重点課題イイb 森林生態系における生物群集の動態の解明
- 編集・発行:森林総合研究所
- 発行日:平成23年3月
- ISBN:978-4-902606-94-2
目次
課題群イイb1 「森林に依存して生育する生物の種間相互作用等の解明」
- 天然に生息するカビでスギ花粉の飛散を防止する
-菌類を用いたスギ花粉飛散防止処理液の開発-
スギ雄花を枯死させて花粉の飛散を抑止する細菌や菌類を探索した結果、スギ黒点病菌の同定、その感染経路の解明、また処理液を考案することで、人為的に花粉の飛散を抑止する方法を完成しました。
- 生物防除素材としてのスズメバチタマセンチュウの評価
スズメバチ女王を不妊にする新種の寄生線虫の生態を明らかにし、利用法を探りました。
- 空中を浮遊している菌類で森の状態を調べる
空中浮遊菌類の種類を調べ、森の状態を調べる指標として利用できるような微生物多様性プロファイル作成法を検討した結果、エアサンプラーで菌類を捕捉・同定することで、各調査地における菌類の多様性プロファイルが作成できることが分かりました。
- 森林害虫における音・振動を介した相互作用の解明
音や振動を用いた忌避・交信阻害等による森林害虫防除技術の開発につなげるべく、音・振動を介した種内、種間関係を解明し、害虫が利用する音・振動とその役割のプロファイルを作成しました。
課題群イイb2 「森林生態系を構成する生物個体群及び群集の動態の解明」
- 大気オゾン濃度の上昇は樹木の二酸化炭素吸収量を低下させる
樹冠内の光環境を考慮することで、オゾン濃度上昇による樹木の光合成反応への影響を明らかにしました。
- 大気二酸化炭素濃度の上昇と土壌の乾燥によって樹木の光合成はどのように変化するのか
高二酸化炭素環境下での森林による二酸化炭素吸収量を正確に推定するためには、土壌の水分条件を考慮に入れて光合成反応を予測する必要があることを明らかにしました。
- 芽生えから大木まで多種多様な樹木呼吸を表す新モデル式
「樹木個体呼吸と個体サイズ」の関係は森林のCO2収支を検討する基礎情報です。熱帯~シベリアの樹木の芽生えから大木まで63種の多種多様な271個体を測定した結果、樹木個体呼吸は二つの異なる原理で変化することがわかりました。
- ササ類の生育域を気候条件から予測する
日本の冷温帯・亜高山帯林の林床優占種であるチシマザサとチマキザサについて、分布を規定する気候要因とその閾値を明らかにするモデルを構築し、現在と100 年後の生育可能な地域(潜在生育域)を明らかにしました。
- 競争を生き抜くブナの若木の戦略:成長にあわせて体形を変える
ブナの若木は、成長にともない変化する周囲植物との競争関係にあわせ、それぞれの局面にふさわしい樹形をとることで競争を生き抜いていることを明らかにしました。
- 台風撹乱に強い照葉樹林
—長期生態研究が明らかにする森林の維持機構—
成熟林と二次林の、大型台風による撹乱による被害形態を比較解析を行って、照葉樹林の高い台風への耐性は、複雑な階層構造と豊かな種組成が貢献していることが明らかになりました。
- 大規模撹乱から森はよみがえったか?
—御岳山崩れ森林回復の軌跡—
大規模な山崩れ跡地の自然回復の見込みを検討するため、植生遷移の過程を四半世紀にわたって観測してきました。
- 分布北限域のブナは、撹乱を契機として分布を拡大した
ブナの自生最北限におけるブナ林の成立過程を、地形情報・年輪解析・倒木片の樹種判別、過去の撹乱の歴史などの情報から推定しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.
