ここから本文です。
研究レポート
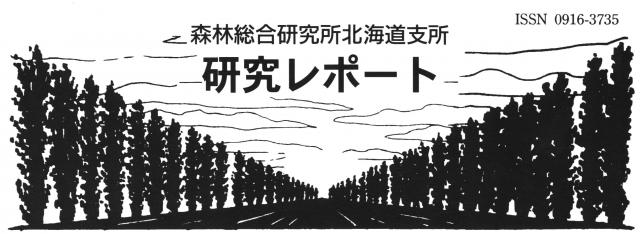
○研究レポートは、No.100で終刊となりました。2008年12月より、新たな広報誌「北の森だより」を発行しております。
| ◆研究レポート | ||
|---|---|---|
| No. | 発行年月 | タイトル名(著者名) |
| 100 | 2008.03 | 台風による風倒被害が土壌呼吸に与える影響-2004年9月の台風18号による森林被害-(阪田匡司、酒井寿夫、相澤州平、宇都木玄、石塚成宏、酒井佳美、田中永晴) |
| 99 |
2008.02 |
スズメバチの女王を不妊化する寄生線虫(佐山勝彦、小坂肇、牧野俊一(森林昆虫領域)) |
| 98 |
2008.01 |
高CO2環境下における樹木の光合成反応予測-水分条件の影響-(北尾光俊) |
| 97 |
2007.11 |
レブンアツモリソウの保全生物学(河原孝行、山下直子(関西支所)) |
| 96 |
2007.10 |
トドマツの水食い材(松崎智徳) |
| 95 |
2007.09 |
在来のマルハナバチに脅威!-外来種セイヨウオオマルハナバチの野生化-(永光輝義) |
| 94 |
2007.03 |
ニホンテンによるスズメバチの巣の捕食(平川浩文、佐山勝彦) |
|
2007.02 |
樹木葉のCO2を吸収するための巧みな戦略(上村章) | |
| 92 |
2007.01 |
CO2濃度の上昇がケヤマハンノキの成長に及ぼす影響(飛田博順) |
|
2006.12 |
鳥の声を録音して、森にすむ鳥を調べる-森林性鳥類のモニタリングの可能性を探る-(松岡茂) | |
|
2006.11 |
林冠内の葉の分布には、どんな意味があるの?(宇都木玄) | |
| 89 | 2006.10 | 温暖化による日本のブナ林への影響(松井哲哉、田中信行、垰田宏、八木橋勉(国際農林水産業研究センター)) |
| 88 |
2006.03 |
世界自然遺産をどのように管理するか?(庄司康(北海道大学大学院農学研究科)八巻一成、駒木貴彰) |
| 87 |
2006.03 |
アシナガバチ社会の成り立ち-巣の中の血縁関係をさぐる-(佐山勝彦) |
| 86 |
2006.01 |
台風による風倒被害を受けた森林のCO2フラックス-2004年9月の台風18号による森林被害-(北村兼三、山野井克己、中井裕一郎、鈴木覚(気象環境研究領域)) |
| 85 |
2005.12 |
アカエゾマツは春先、一時的に低温害を受けやすくなる(北尾 光俊) |
| 84 |
2005.10 |
幾寅天然林における択伐作業による林分被害について-望ましい択抜方式をめざして-(佐々木尚三) |
|
2005.07 |
空から見た風倒害-2004年台風が森林に遺した爪痕を探し求める-(鷹尾 元) | |
|
2005.03 |
長伐期化に対応したカラマツ人工林収穫予想表(石橋 聡、鷹尾 元、髙橋正義、猪瀬光雄) | |
| 81 |
2005.02 |
トドマツの凍裂-北海道各地の出現状況について-(松崎智徳) |
| 80 |
2005.01 |
森林におけるCO2出入りの仕組みは複雑だ(宇都木玄) |
| 79 |
2004.11 |
上から下から測ったシベリアのカラマツ林(鷹尾 元) |
| 78 | 2004.08 | DNAを調べてわかること-西日本のツキノワグマの歴史を探る-(石橋 靖幸) |
| 77 | 2004.07 | 氷河期の生き残り:ヤチカンバ(永光 輝義) |
| 76 | 2004.03 | トドマツの仮道管長(松崎智徳) |
| 75 | 2004.03 | 乾燥ストレスが光合成に与える影響(北尾光俊) |
| 74 | 2004.02 | 森林土壌における温室効果ガス発生・吸収の実態(石塚 成宏、阪田 匡司、高橋 正通、田中 永晴) |
| 73 | 2003.10 | 森林生態系の健全性評価手法(丸山 温,北尾光俊,飛田博順,山口岳広) |
| 72 | 2003.10 | 北方系落葉広葉樹林における大気-森林間のCO2交換量(中井裕一郎,北村兼三,鈴木覚) |
| 71 | 2003.08 | 樹洞内観察記録装置の開発-生物多様性の保全をめざして-(松岡茂) |
| 70 | 2003.08 | 定山渓森林理水試験地の水収支(北村兼三,中井裕一郎,鈴木覚) |
| 69 | 2003.04 | 自動撮影が切り開く新しい哺乳類研究のアプローチ(平川浩文) |
| 68 | 2003.03 | アジア熱帯林における土壌CO2フラックスの空間依存性(石塚成宏,中島泰弘(農環研),米村正一郎(農環研),鶴田治雄(東京農工大),イスワンディ・アナス(ボゴール農科大),ダニエル・ムルディヤルソー(ボゴール農科大)) |
| 67 | 2003.03 | 札幌周辺里山の植物の多様性にせまる(河原孝行・飯田滋生(海外研究領域派遣職員(JICA)) |
| 66 | 2003.01 | 森林作業に利用するベースマシンの開発研究について-全方向移動車両TTM-(佐々木尚三) |
| 65 |
2002.11 |
衛生画像で再現したロシア極東の森林撹乱の履歴(鷹尾元) |
| 64 |
2002.03 |
落葉広葉樹林における雪面からのCO2放出量(鈴木 覚・中井裕一郎・北村兼三) |
| 63 | 2002.01 | 道東トドマツ造林地に発生した集団枯損(丸山温・尾崎研一・中井裕一郎・黒田慶子(関西支所)・坂本知己(気象環境研究領域)・福山研二(林野庁)) |
| 62 | 2001.12 | SSRマーカーを用いたカラマツの連鎖地図作成と主要形態形質のQTLマッピング(河原孝行・永光輝義・松崎智徳・織部雄一郎) |
| 61 | 2001.09 | ヤナギ類水紋病の研究-北海道における発生と発病機構の解明-(坂本泰明) |
| 60 | 2001.09 | 火山放出物未熟土に生育する北方造林樹種の地下部バイオマス(酒井佳美・高橋正通・松浦陽次郎・石塚成宏・田中永晴) |
| 59 | 2001.08 | 森林所有者の経営動向と今後の森林施策のあり方(駒木貴彰) |
| 58 | 2001.03 | 有珠山2000年噴火による森林被害の評価(阿部真・田内裕之・飯田滋生) |
| 57 | 2001.01 | キツツキ営巣木の樹幹内部の特徴を知る試み-立ち木の木材の硬さを計る方法-(松岡茂) |
| 56 | 2000.10 | 有珠山2000年噴火噴出物の化学性について(速報)(田中永晴・寺嶋智巳・白井知樹・鈴木覚・中井裕一郎) |
| 55 | 2000.10 | 開放地と林床のクマイザサ群落の蒸散量(北村兼三・中井裕一郎・坂本知己・寺嶋智巳・白井知樹) |
| 54 | 2000.08 | 有珠山2000年噴火噴出物の透水性について(速報)(寺嶋智巳・白井知樹・鈴木覚・田中永晴・中井裕一郎) |
| 53 | 2000.08 | 札幌羊ヶ丘のウダイカンバ人工林に発生した腐朽・変色被害(山口岳広) |
| 52 | 2000.03 | 大雪山系針葉樹天然林における倒木更新(飯田滋生,阿部真,田内裕之) |
| 51 | 2000.01 | 森林空間の「自然らしさ」を保つために-利用体験の多様性に着目した計画手法の開発-(八巻一成) |
| 50 | 1999.12 | 森林の小面積の伐採は,土壌動物にどのような影響を与えるのか(福山研二・松浦陽次郎) |
| 49 | 1999.05 | トドマツの産地特性-直径,心材含水率,容積密度について-(松崎智徳) |
| 48 | 1999.03 | 森林流域から浮遊土砂はどのように出てくるか(坂本知己・寺嶋智巳・中井裕一郎・北村兼三・白井知樹) |
| 47 | 1998.10 | イチイ力タカイガラムシの防ぎ方-剪定や下草刈りは効果があるのか-(尾崎研一) |
| 46 | 1998.06 | 地球の炭素分布と森林土壌の炭素量(高橋正通・真田悦子) |
| 45 | 1998.02 | 樹木園の花便り(真田勝・坂上勉) |
| 44 | 1997.11 | 北方系森林おける二酸化炭素固定量の推定(佐野真・石橋聡・小木和彦・白石則彦) |
| 43 | 1997.08 | かわいい子には旅をさせろ-稚樹の分布に与える、母樹の影響-(福山研二) |
| 42 | 1997.05 | 「しおれにくさ」を指標とする北方産樹種の乾燥耐性(丸山温・北尾光俊・森茂太) |
| 41 | 1997.03 | 東シベリア、永久凍土連続分布帯における生態系の土壌特性(松浦陽次郎) |
| 40 | 1997.01 | 渓畔域におけるヤナギ類の分布と類型区分図との関係(佐野真・小木和彦・白石則彦・石橋聡) |
| 39 | 1996.10 | ヤブサメの繁殖生活(川路則友) |
| 38 |
1996.08 |
糞を食べる-ウサギ達の巧みな食生活(平川浩文) |
| 37 | 1996.07 | 平成5年の冷害は農林家にどのような影響を与えたか(天野智将・八巻一成) |
| 36 | 1996.03 | ウダイカンバの樹皮色と心材率(田中京子・長坂壽俊・松崎智徳) トドマツ産地による心材含水率のちがい(中村和子・松崎智徳・長坂壽俊) 北海道におけるトドマツの水食い材(中村和子・松崎智徳・今川一志・真田勝) |
| 35 | 1996.03 | 健全なホオノキ種子の選び方 他殖種子をより多く採る方法(中村和子・石田清) ウダイカンバの皮目幅と心材率(田中京子・長坂壽俊・松崎智徳) トドマツの産地による成長のちがい(中村和子・松崎智徳・長坂壽俊) |
| 34 | 1996.02 | 健全なホオノキ種子の選び方 他殖種子をより多く採る方法(中村和子・石田清) ウダイカンバの皮目幅と心材率(田中京子・長坂壽俊・松崎智徳) トドマツの産地による成長のちがい(中村和子・松崎智徳・長坂壽俊) |
| 33 | 1995.10 | イヌエンジュの新病害-がんしゅ細菌病-(坂本泰明) |
| 32 | 1995.08 | 林内地表にみられる凹地形と凸地形の土壌水分および地温の比較(真田悦子・高橋正通・松浦陽次郎) 超音波測距器を用いた樹高測定(白石則彦) |
| 31 | 1995.03 | 幼齢造林地のクモ類の生態-クモを利用したアブラムシの被害軽減技術開発をめざして-(秋田米治) |
| 30 | 1994.07 | 新しい幹曲線式を利用したトドマツの細り表(猪瀬光雄・佐野真・石橋聡) |
| 29 | 1993.12 | 新しい密度管理図を用いたトドマツの収穫予想表(猪瀬光雄・佐野真・石橋聡) |
| 28 | 1991.10 | ユキザサの裁培(柴田彌生) |
| 27 | 1991.10 | 全天写真を利用した簡便な林内気温の推定法(齋藤武史) |
| 26 | 1991.07 | トドマツの林分密度管理指針(猪瀬光雄・佐野真・小木和彦・眞邉昭) |
| 25 | 1991.03 | 落葉広葉樹の光の利用の仕方-光合成特性-(小池孝良) |
| 24 | 1990.06 | トドマツ造林木の幹型と立木幹材積表(小木和彦・猪瀬光雄・佐野真・眞邉昭) |
| 23 | 1990.03 | 森林病虫獣の発生と被害を防ぐために~北海道における発生情報の収集・記録と解析~(小泉力) |
| 22 | 1989.12 | トドマツ造林地の放牧試験(柴田弥生・馬場強逸・高畑滋・中田功・横山長蔵・毛利勝四郎) |
| 21 | 1989.12 | シラカンバ、ヤチダモ、ミズナラ苗木の重量成長特性(藤村好子) |
| 20 | 1989.12 | カンバ類の林分密度管理図〈暫定〉(猪瀬光雄・小木和彦・佐野真) |
| 19 | 1988.03 | 天然林の林冠構造-その実態と施業後の構造-(岸田昭雄・向出弘正・中村和子) |
| 18 | 1988.02 | 山地斜面の安定度評価とその保全対策(遠藤泰造) |
| 17 | 1987.10 | トドマツ枝枯病被害危険地帯区分図(吉武孝) |
| 16 | 1987.03 | 土地利用の相違による土壌水分の変化(清水晃) |
| 15 | 1987.03 | 風害等の林冠破壊による土壌の変化(塩崎正雄) |
| 14 | 1987.02 | 力ラマツ林分の本数密度と年輪幅(猪瀬光雄) |
| 13 | 1986.11 | 貯水能を考慮した山地流域の最大流量の略算式(遠藤泰造) |
| ◆新技術情報 | ||
| 12 | 1985.08 | トドマツ林分の本数密度と年輪幅(猪瀬光雄) |
| 11 | 1984.06 | 林業経営における超小型コンピュータの利用(向出弘正) |
| 10 | 1984.01 | 北海道ササ分布図(豊岡洪・佐藤明・石塚森吉) |
| 9 | 1983.09 | ノウサギの生息数調査法(柴田義春) |
| 8 | 1983.06 | 公園緑地の土壌と樹木の生長(真田勝) |
| 7 | 1983.03 | 移植と苗木の生理(高橋邦秀) |
| 6 | 1983.01 | 北海道積雪分布図(平均最深)(増田久夫) |
| 5 | 1982.03 | 密度管理図の適合度の改善(真辺昭) |
| 4 | 1981.03 | トドマツ苗の凍結温度による晩霜被害率の推定(坂上幸雄・藤村好子) |
| 3 | 1979.04 | トドマツオオアブラの総合防除(高井正利・古田公人) |
| 2 | 1979.03 | 林業地帯における月平均気温推定法(増田久夫) |
| 1 | 1978.10 | 菌害防除による更新法(遠藤克昭) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.
