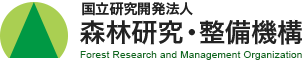ホーム > 公開情報 > 法定公開情報 > 環境への取組 > 森林研究・整備機構 環境報告書2024 > TOP MESSAGE
更新日:2024年9月30日
ここから本文です。
TOP MESSAGE
森林を通じて持続可能な社会へ
| 国立研究開発法人森林研究・整備機構 理事長 |
 |
 |
国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「森林研究・整備機構」という。)は、森林・林業・木材産業と林木育種分野を総合的に扱う我が国唯一の試験研究機関である森林総合研究所と、水源林造成業務を担う森林整備センター及び森林保険業務を担う森林保険センターの3つのグループからなり、北海道から九州・沖縄まで日本全国にわたって拠点を設置して、全国的に森林に関する様々な業務を展開しています。
森林は、水循環や大気中の二酸化炭素吸収への深い関わりを通じて、人類の生存に必要な地球環境を形成するとともに、国土保全、水源涵養(かんよう)、林産物生産などの多面的機能によって私たちの日常生活を支えています。我が国は山地が多く、国土の7割が森林で覆われていますが、その森林の4割は人の手によって造成されてきた人工林で、現在の森林の恵みは先人たちの努力の賜物です。そして、その多様な恵みを今後も享受していくためには、将来にわたって持続的に森林の保全や整備を進めていく必要があります。
国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成には、森林資源の持続可能な利用はもちろん、森林が持つ多面的機能が重要な役割を果たすと期待されています。また、2016年に発効したパリ協定の目標の達成のために、2050年までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにする取組が世界的に進められている中、我が国においても2050年カーボンニュートラルの実現に向け各方面で動きが活発化しています。新型コロナウイルス感染拡大防止対策を機に、テレワークの普及を含め、新しい生活様式に関する議論が進みました。気候変化の問題だけでなく、防災・減災、健康問題などに関連しても、「自然に根差した社会問題の解決」が注目されています。森林・林業・木材産業を取り巻く環境の変化を踏まえ、分散型社会の構築やデジタル技術によるイノベーションの推進、再生可能な新素材開発、など新たな役割を果たすことが求められています。
森林研究・整備機構は、こうした国内外の様々な課題解決に向け、科学技術、行政施策、社会経済活動、国際協力に貢献することを目的に、令和3年度から第5期中長期計画を定めています。研究・技術開発面では、(1)環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発、(2)森林資源の活用による循環型社会の実現と山村振興に資する研究開発、(3)多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種、の3つを重点課題として、気候変動の緩和と適応、生物多様性や生態系サービスの保全などに関する研究に取り組むとともに、持続的な林業システムの構築や木質資源の有効利用技術の開発、生産性や二酸化炭素吸収能力が高いだけでなく花粉生産量の少ない品種の開発・普及などを推進しています。水源林造成事業では、公益的機能の高い奥地水源林の整備のため、伐期の長期化をにらんだ複層林施業や、契約地周辺も考慮した面的な整備に力を入れています。また、健全な林業経営の支援のため、森林保険制度の適切な運営やグリーンボンドによる資産運用も進めています。近年のグリーントランスフォーメーション(GX)やカーボンニュートラル、ネイチャーポジティブ、バイオエコノミーなどの議論はこの目標と合致するものと考えています。令和5年度においても、こうした新しい動向を十分意識しながら、中長期目標の達成に向けて取組を進めてきました。
第5期中長期目標の達成には、森林に関わる関係省庁、産業界、教育機関、森林所有者、森林の恵みを受け取る国民の皆様、さらには国際機関との連携を密にすることが必須です。その中で、森林研究・整備機構は総合力を発揮する中核的機関としての役割を担い、これまでの取組を一層発展させたいと考えています。
当機構の取組の推進に対し、御協力いただいている関係者の皆様に、あらためて感謝申し上げますとともに、今後とも引き続き、一層の皆様のご協力、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、私からのメッセージとさせていただきます。
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.